上巻の帯に「悩める天才」 とあるが、それもさることながら「進軍の巨人」というべき かもしれない。
長い、じつに長い本であった。上下あわせて900ページ超。読み終えるまで3日かかったが、正直いって、読むのにくたびれてしまった。イーロン・マスク(Elon Musk)という「超人」が、止まることなく「進軍」している、そのエネルギーの熱量 のせいだろう。
上巻の途中からぐんぐん面白くなってくるが、読者は最後の最後までイーロンに振り回されっぱなし である。
レオナルド・ダヴィンチから始まり、アインシュタインからスティーブ・ジョブズまで、「天才の伝記」を書かせたら右にでる者はいないという、 伝記作家で経営者のアイザックソン氏。2年間にわたって密着取材を行ったとのことだが、それはおなじだったのでは ないか?
イーロンの下で働いてきた人たちにとっては、言うまでもない。いや、現在進行形で振り回されている。
上下あわせて全95章。ほぼ時間軸に沿って進行していく形式 になっているのは、イーロンがスペースX や テスラ といったハイテク製造業 だけでなく、それ以外のニューラルリンク 、さらにはまた昨年2022年からはSNSのツイッター(現在はX)まで同時進行 させているからだ。
(とある書店の店頭ショーウィンドウに飾られているもの)
下巻は、2020年から2023年まで、足かけ4年の現在進行形の出来事を、リアルタイムで中継しているような記述 である。
とりあえず、2023年4月で中継が終わっている が、まだまだ現在進行形で進軍がつづいている。オープンエンドなのである。
■かつてのモーレツな日本企業と日本人のような
だが、そんな「常識」をはなから無視しているのがイーロン・マスク だ。現時点で、全部で6つの会社を陣頭指揮 しているのである。
「超人的」というよりも、「超人」そのもの ではないか!
「撃ちてしやまん」という、日中戦争下の日本のスローガンを想起させるものがある。敵を打ち破るまで戦いはやめるな、というマインドセットである。
しかも、徹底した「現場主義」であり、「コスト削減の鬼」といってもいいマイクロマネジメントの実行者 である。まるでかつての日本の製造業 のようだ。
経営者が現場で寝泊まりするのも当たり前 、朝から夜中まで働きづめ で、いきなり深夜に部下に召集をかけることもたびたび である。昔風にいえばモーレツ社長そのものだ。現在の日本なら、ブラック企業だとして糾弾されることだろう。
無茶ぶりに見えるが、生産管理の世界でいう「ムリ・ムダ・ムラをなくせ」というセオリーどおり である。その実現のためには無茶も必要だということだ。
マーケティング依存の「マーケットイン」ではなく、製品そのものが魅力的ですばらしければ、かならず売れるはずだという「プロダクトアウト」 の発想。ビジョンの実現と危機感の解決のためには、目に見えるカタチとしての、魅力ある製品がなければ説得力がない という哲学。
需要はつくるものだという信念 であり、そのためには徹底して設計と製造の融合を実行 させる。サプライチェーンは短ければ短いほうがいい。だからアウトソーシングや系列化など論外で、部品からすべて内製化すべし というの姿勢。
製品ユーザーとの距離は、近ければ近いほうが開発には都合がいい 。だから、工場は市場の近くにつくる。米国と中国とドイツである。
アイデアはおなじ空間で働いているほうが生まれやすい から、リモートワークはダメだ、全員出社せよ。まるでホンダの「ワイガヤ」だな。
考えてみれば、自分自身の経験を振り返っても、日本企業も昔はこんなこと当たり前だった ような気もする。それだけ、日本企業にも、日本製品に魅力がなくなってしまったということか。日本は進むべき方向を間違っているのかも しれない。
だからこそ、イーロン・マスクのような存在は、日本にも必要だ。こんな超人と付き合うのは、それこそミッション・インポッシブル(=実行不可能なミッション) であろう。とはいえ、過激にみられがちなイーロンの言動だが、日本企業にとってもヒントになることは多い のではないか?
たとえば、ミニカーなどおもちゃが量産プロセス構築において参考になる という話や、部品点数はできるだけ減らしてミニマムに する、マテリアル(素材)への注目 などなどである。
そんなヒントが、イーロン自身の発言として、この本のなかには無数にちりばめられている。ディテールにも注目してほしい。
VIDEO
(Author Walter Isaacson talks new Elon Musk biography)
■イノベーションはクレージーな人間の意思と行動なしには生まれない
ミッション・インポッシブルであればあるほど燃える男 。困難や苦難はエネルギー源なのだ。アドレナリン出しっ放しである。
飽きてしまうことをなによりも恐れている男 。何もしていないことに耐えられない男 。無理矢理にでも問題をつくりだしては、みずからをむち打つだけでなく、関係する人びとを巻き込んで尻を叩きまくる。
超絶的なワーカホリック 。「ワーク・ライフ・バランス」などということばは、イーロンの辞書にはないのだろう。「ワーク・イズ・ライフ」 なのだ。
どう考えても実現不可能としか思えないデッドライン設定して公表 し、自分とチームを崖っぷちに追い込む 。修羅場。切迫感。無茶ぶり 。実現不能と思える高い目標を設定して、みずからが先頭にたってチーム全体を追い込む姿勢。
たしかに、そうでもしなければイノベーションなど生まれない こともたしかだ。人間は追い詰められて、追い詰められて、はじめて局面打開の知恵 が生まれてくる。いや、降ってくるというべきか。
火星ミッション実現のための第一歩である、民間企業のスペースX が存在しなければ、米国の宇宙開発は過去の話になってしまっていた ことだろう。
「スターリンク」がなければ、ウクライナは戦いつづけることなどできなかった だろう(*ただし、イーロン・マスク自身は、スターリンクはあくまでも民生利用に限定したいようだ)。
いまだ道半ばとはいえ、「テスラ」が存在しなければ、ロボタクシーなどの自律走行の自動運転など夢のまた夢 というところだろう。
アイザックソン氏が巻頭に記したイーロン・マスクとスティーブ・ジョブズのことば は、説得力をもって迫ってくる。
最後まで読み終えて、ふたたび巻頭にもどってその2つのことばを読むと、心の底から納得しないわけにはいかない。
感情を逆なでしてしまった方々に、一言、申し上げたい。
本気で思われるのですか、と。(イーロン・マスク、2021年5月8日)
自分が世界を変えられると本気で信じるクレイジーな人 こそが、
ただし、イーロン・マスクとスティーブ・ジョブズには決定的な違い がある。
これに対して、イーロン・マスクは真逆 である。デザインだけでなく、製造も自分でやらなくてはダメだ という姿勢である。
その意味では、同類でありながらも、イーロン・マスクはスティーブ・ジョブズのアンチテーゼ であり、かつての日本企業のデジタル時代における「超進化形」 といえるかもしれない。
日本の企業人も再考が必要だろう。
■本人は人間にはあまり関心がないが、その人物そのものは好奇心を誘発する存在
イーロン・マスクという「人間」は、事業以外の側面でも面白い。
ビジネス活動をつうじて、「人類」を救うという壮大なビジョン実現 には邁進するが、個別の「人間」関係にはほとんど関心がない 。アスベルガーを自称していることもあり、脳の配線がどうも一般人とは違うようだ。
VIDEO
(イーロン・マスクがモデル?といわれる映画『アイアンマン』2008年)
複数の女性とのあいだに子どもを何人もつくっているが、その多くが人工授精や代理母をつかっている。人類の数を減らすなという理由もあるようだが、どこまで本気なのかでまかせなのかわからない。
浴びせられてきた金持ち批判に嫌気がさして、不動産をすべて売却 してしまい、転々と住む場所を変えながら生活している。コレクションや所有には関心はないのである。
そもそも金儲けじたいが目的ではなく、しかも慈善事業にもほとんど関心がない 。かれにとっては、ビジネス活動そのものが、人類への貢献 なのである。その意味では、松下幸之助にも通じるものがあるというべきかもしれない。
みずからが信じる「フロンティア開拓」に全財産をつぎ込む姿勢 。掛け金をずべてぶち込む「オールイン」型の新事業投資 。のるかそるか、である。
リスクテイカーなんていうレベルではない。ほとんどギャンブルである。リーマンショックの2008年には、それこそ破綻すれすれまでの財務的綱渡り を演じている。それにしても壮絶だが、もしかすると無意識レベルでは破滅願望があるのかもしれない。
「AIが人間を凌駕させないための戦い」はドンキホーテ的 でさえあるが、こういう人は世の中には必要だろう。
(Optimus, aka Tesla Bot Wikipediaより)
テスラで開発をつづける「人型ロボットのオプティマス」 もまたその一つである。
遠隔操作するロボットではなく、ロボット自身に人間の言動を「学習」させるヒューマノイドを開発する という姿勢。さすがである。「学習」という点にかんしては、わが子の X の成長ぶりも参考に なっているようだ。
そんなイーロンにとって、機械学習のデータ源として、テスラによる動画だけでなく、ツイッターに投稿される文章や画像や動画もつかえることがわかったというのは、予期せぬ副産物 だったようだ。
■はたして火星にコロニーが建設されるのはいつの日か?
壮大なビジョンと強い危機感 。最初から最後まで振り回されっぱなしで、ついていくのはたいへんだ。アイザックソン氏によるこの評伝は、まさにイーロン・マスクそのもの である。
「撃ちてし止まん」タイプの超人。こんな人間こそイノベーターとして、「フロンティア開拓」を行うのである。サイエンス・フィクション(SF)から、フィクションを取り除く とのがかれのミッションだ。
はたして、かれが生きているうちに火星にコロニーはつくれるのか? いつまで走りつづけることができるのか?
おそらく、というより間違いなく、枯れるということはないだろう 。ある日、突然バタンと倒れて終わる。 そんなことになるのだろう。まさに「撃ちてしやまん」である。
とはいえ、現在進行形のイーロン・マスクは、まだまだ当分のあいだ目が離せない存在であり続けることは間違いない。
すでに70歳を超えているアイザックソン氏に、続編を書くことはあるのだろうか? 文庫化される際には多少の追補がなされるであろうが・・・。
(画像をクリック! )
<関連サイト>
(南アフリカでの子ども時代のイーロン)
「講談社の書籍紹介」より
驚異的な頭脳と集中力、激しすぎる情熱とパワーで、宇宙ロケットからスタイリッシュな電気自動車まで「不可能」を次々と実現させてきた男――。
シリコンバレーがハリウッド化し、単純なアプリや広告を垂れ流す仕組みを作った経営者ばかりが持てはやされる中、リアルの世界で重厚長大な本物のイノベーションを巻き起こしてきた男 ――。「人類の火星移住を実現させる」という壮大な夢(パーパス)を抱き、そのためにはどんなリスクにも果敢に挑み、周囲の摩擦や軋轢などモノともしない男――。いま、世界がもっとも注目する経営者イーロン・マスクの本格伝記がついに登場!イジメにあった少年時代、祖国・南アフリカから逃避、駆け出しの経営者時代からペイパル創業を経て、ついにロケットの世界へ・・・・・・彼の半生が明らかになります。(
講談社BOOK倶楽部『イーロン・マスク 未来を創る男』 )
<関連記事>
(2023年12月20日 情報追加)
<ブログ内関連記事>
■先行する「天才」起業家。同類のモーレツなディスラプター
■イノベーションとディスラプション
・・本業に専念し、それ以外はアウトソーシングするという「京都モデル」は、サプライチェーンを極限まで短くするために内製化を徹底するというイーロン・マスクの製造業哲学とは真逆の立場
■宇宙ビジネスと火星移住
■人型ロボット
■イーロン・マスクの原点である南アフリカ
(2025年2月22日 情報追加)
(2025年1月24日発売の拙著です 画像をクリック! )
(2023年11月25日発売の拙著です 画像をクリック! )
(2022年12月23日発売の拙著です 画像をクリック! )
(2022年6月24日発売の拙著です 画像をクリック! )
(2021年11月19日発売の拙著です 画像をクリック! )
(2021年10月22日発売の拙著です 画像をクリック! )
(2020年12月18日発売の拙著です 画像をクリック! )
(2020年5月28日発売の拙著です 画像をクリック! )
(2019年4月27日発売の拙著です 画像をクリック! )
(2017年5月19日発売の拙著です 画像をクリック! )
(2012年7月3日発売の拙著です 画像をクリック! )
ケン・マネジメントのウェブサイトは
ご意見・ご感想・ご質問は ken@kensatoken.com にどうぞ。
お手数ですが、クリック&ペーストでお願いします。
禁無断転載!
end













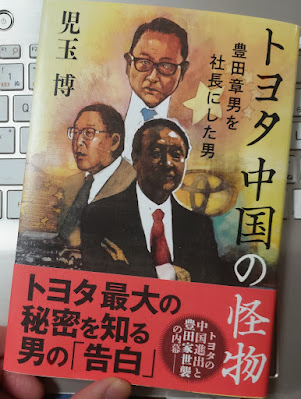



.png)

.png)
.png)
.png)






































