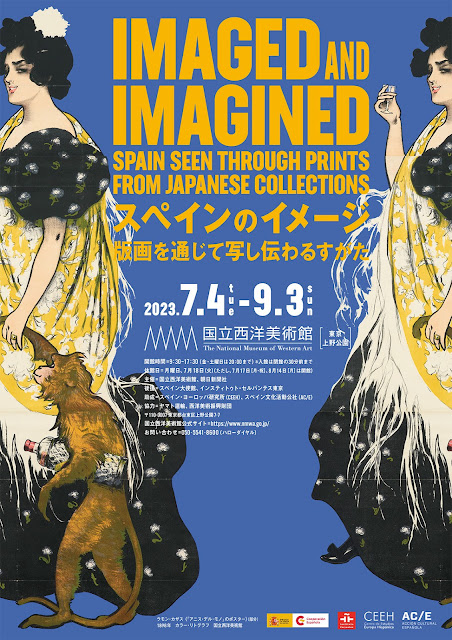美術展「異端の奇才 オーブリー・ビアズリー展」(三菱一号館美術館)を見に行ってきた。
丸紅でボッティチェリを見たあとは、大手町を経由して丸の内へ移動。散歩としては、このくらいの距離がちょうどいい。
ビアズリーといえば、オスカー・ワイルドの『サロメ』、オスカー・ワイルドの『サロメ』といえばビアズリー。そんなイメージが定着している。
(福田恆存訳の『サロメ』)
『サロメ』は新約聖書に登場する物語である。サロメといえば、ギュスターヴ・モローの幻想的な絵画を想起する。
物語の影響はリリアーナ・カヴァーニ監督の映画『愛の嵐』(The Night Porter 1974年)にまで及んでいる。お皿に載せられた生首という、倒錯的で猟奇的なシーン!
ビアズリーにはじめて出会ったのは高校時代のことだ。神田の古書店街で英国で出版された画集を手にして、その妖しい魅力に魅入られてしまった。 ビアズリー独自の二次元的でフラットな黒白の線描画の世界。オスカー・ワイルドの作品も好きで英語で読んでいるが、なぜか日本語訳で読んだことはない。
(マイコレクションよりビアズリーとオスカー・ワイルド)
そんなビアズリーの本格的な美術展である。三菱一号館美術館は、11年前の2014年にも「ザ・ビューティフル 英国の唯美主義1860 ~ 1900」を開催している。ビジネスをつうじて全盛期の大英帝国と縁の深かった三菱ならでは、といえよう。
基本的に独学で絵画を習得したオーブリー・ビアズリーだが、オスカー・ワイルドもビアズリーもまた、19世紀末英国の日本趣味(アングロ・ジャパニーズ)の影響下にある。そしてビアズリーは、再帰的に日本にも影響をあたえている。
今回の美術展では言及がなかったが、大正時代に谷崎潤一郎の『人魚の嘆き』の装画を担当した水島爾保布(みずしま・にほふ)のことを想起したい。かれには「ビアズリー張りの」という形容詞が冠せられている。
(文庫版はサイズが小さいのが残念だが・・)
日本に影響され、ふたたび日本に影響するという、玉突きのような影響関係は、構図において浮世絵の影響下にあるフランス印象派と似ているかもしれない。顔を描く際に鼻を描かない後期ビアズリーの手法は、現代日本のマンガやアニメと共通しているような気もする。
(図録より「恋文」 鼻が描かれていないことに注目!)
今回の美術展の監修をおこなったの河村錠一郎・一橋大学名誉教授は、英語と英文学、そして美術史が専門の学者だ。
40年以上も前のことだが、大学学部時代にはスライドを多用した河村教授の西洋美術史の講義を受講し、大いに蒙を啓かれた経験をしている。
とくに新プラトン主義の影響下にあった、ルネサンス後期からマニエリスム期へや、英国やベルギーの世紀末美術の講義が印象に残っている。
(画像をクリック!)
■切っても切れないはずのビアズリーとオスカー・ワイルドだが・・・
さて、ビアズリーといえば、オスカー・ワイルドの『サロメ』というイメージが固定化している。
ところが、ワイルド自身はかならずしもビアズリーのイラストには満足ではなかったらしい。そんな話は、この美術展ではじめて知った。
ビアズリーとオスカー・ワイルドの複雑な関係については、美術史を題材にした原田マハの『サロメ』という小説を読むといい。もちろんフィクションではあるが、ファクトをベースにして作家の想像力で補った作品だ。イメージを膨らませることができるだろう。
前期の代表作は、デビューにつながった『アーサー王の死』である。
後期のビアズリーには、古代ギリシアの喜劇作家アリストパネースの『女の平和』(リューシストラテー)の挿絵もある。
男性性器を肥大化して描く猥褻でカリカチュア的な手法は、日本の浮世絵春画の影響があるのだろうか。これらの作品は「18禁!」のスペースに展示されているのでお楽しみに。
ビアズリーの画集はもっているので、あえて『図録』(3,500円)は購入しなかったが、マグネット(@650円)は2種類購入した。マイコレクションにまたあらたに加わることになった。
<ブログ内関連記事>
(2023年11月25日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年12月23日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年6月24日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年11月19日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年10月22日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2020年12月18日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2012年7月3日発売の拙著です 画像をクリック!)
end