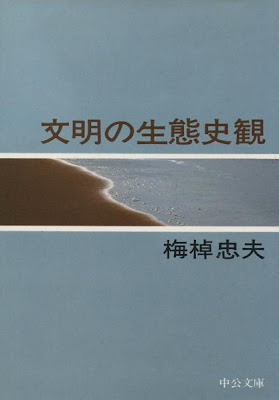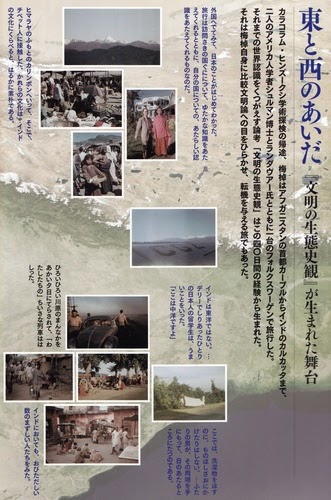■梅棹忠夫の『文明の生態史観』は日本人必読の現代の古典である!・
梅棹忠夫の代表作といえば、『文明の生態史観』であることは、誰にも異存はないだろう。それだけインパクトの大きな論文であったのだ。
わたしがはじめてこの論文が収録された文庫本を読んだのは大学2年のときだったと記憶している。1981年頃の話であるから、いまから30年前の話になる。
正確な記憶がないのだが、この本を知ったキッカケは、推薦図書のリストの一冊にあげられていたのではないかと思う。
社会科学の総合大学に入学したわたしが真っ先に取り組んだのは、マックス・ウェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(・・いわゆる通称「プロ倫」)であったが、『文明の生態史観』もまた、それに劣らず重要な文献であるとされていたはずだ。
1981年当時は、社会科学の分野では、まだまだマルクス主義が勢力を保っていた。ソ連が崩壊したのはそれから10年後、1991年のことであるから、すでに凋落の兆しが見えていたとはいえ、ウェ-バーとならんでマルクスは必読書であったのだった。
梅棹忠夫の 『文明の生態史観』 は、ある意味では自然科学の観点からみた、マルクス主義とは異なる意味での「唯物論的」なものの見方であったといえるかもしれない。
もともと理科少年で、しかも生物と地学が大好きなわたしのような人間にとっては、『文明の生態史観』は、文学作品よりもピンとくる内容であったことは確かだった。しかも、高校時代には小室直樹の一般デビュー作『ソビト帝国の崩壊』をリアルタイムで読んでいたので、共産主義や社会主義に対する幻想をもたないどころか、嫌悪感すらもっていたことも大きい。
大学キャンパスではいまだに社会主義幻想の残滓(ざんし)とでもすべきものは残っていたが、それはビジネスマン養成大学とは、学問的には社会科学が研究対象であったことも大きいだろう。この点については、書評 『革新幻想の戦後史』(竹内洋、中央公論新社、2011)-教育社会学者が「自分史」として語る「革新幻想」時代の「戦後日本」論 も参照していただきたい。
もっとも、バブル経済前夜であり、「西の京大、東の一橋」と語られていたキャンパスは、ちょうどその頃に開業したディズニーランドになぞらえて語られることも多かったのだが。
しかも、わたしが学んだ一橋大学の歴史学においては、社会科学の先達としてのマルクス本人には敬意を表しながらも、唯物史観にもとづく「発展段階説」には否定的であった。つまり、社会科学者としてのマルクスは尊敬しても、唯物史観はイデオロギーに過ぎないという姿勢が強かったのは幸いであった。
この見方は、唯物史観(=マルクス主義) VS. 生態史観(=梅棹理論) という枠組みで、あざやかに整理して見せた歴史学者・川勝平太の一連の著作を読んだことで、おぼろげながらその意味がわかってきたのだが、これはまた別の機会に取り上げることとしよう。
■文明とは? なぜ文化ではなく、文明か?
日本語では、「文化」と「文明」はあまり意識して区別されていないような気もするが、梅棹忠夫はこの両者を明確に区分して使っている。
文化はドイツ語のクルトゥーア(Kultur)に該当するのに対し、文明はフランス語のシヴィリザシオン(civilisation)に該当するという理解もあるが、ドイツ語にもフランス語起源のツィヴィリザチオン(Zvilisation)、フランス語にも文化を意味するキュルチュール(culture)というコトバはある
『文明の生態史観』のなかで、梅棹忠夫はつぎのような表現で、文化と文明の違いについて書いている。引用は「文明の生態史観」という同名の論文から。
戦前は文明国ということばをよくきいた。戦後はもっぱら文化国で、文明をいわなくなったのはどういたことだろうか。戦争にまけて、鼻べちゃになったので、文明国の名を返上したのだろうか。しかし日本は、戦争にまけても、依然として高度の文明国である。ある部分では、戦前よりも文明の度がすすんでさえいる。
いちいち文明の特徴をあげるまでもないが、たとえば、巨大な工業力である。それから、全国にはりめぐされたぼう大な交通通信網。完備した行政組織、教育制度。教育の普及、豊富な物資、生活水準の高さ。たかい平均年齢、ひくい死亡率。発達した学問、芸術。
以後、梅棹忠夫は一貫して「日本文明」という表現を使用していることは、梅棹忠夫の読者なら十二分に了解していることだろう。
なお、『文明の生態史観』(中公文庫版)は、以下の論文から構成されている。( )内は論文の初出年度(・・発表されてない場合は執筆年度)である。
東と西のあいだ (1962年)
東の文化・西の文化 (1956年)
文明の生態史観 (1957年)
新文明世界地図-比較文明論へのさぐり (1957年)
生態史観から見た日本 (1957年)
東南アジアの旅から-文明の生態史観・つづき (1958年)
アラブ民族の命運 (1958年)
東南アジアのインド (1958年)
「中洋」の国ぐに (1961年)
タイからネパールまで-学問・芸術・宗教 (1962年)
比較宗教論への方法論的おぼえがき (1965年)
なお、「東南アジアの旅から-文明の生態史観・つづき」(1958年)の内容を発展させたものが、『東南アジア紀行』となっている。この本については 『東南アジア紀行 上下』(梅棹忠夫、中公文庫、1979 単行本初版 1964) は、"移動図書館" 実行の成果!-梅棹式 "アタマの引き出し" の作り方の実践でもある を参照していただきたい。
■「生態史観」とは何か?-簡単に振り返っておこう
「戦後の日本人に元気を与えた論文」として評価の高い「文明の生態史観」であるが、基本的には「中洋」の発見ということがもっとも大きなポイントであることは言うまでもない。
「中洋」とは「西洋」でも「東洋」でもない、その中間地帯にあるもの。具体的にいえばインド亜大陸(sub-continent)がそれに該当する。
先にも引用したように、梅棹忠夫は「日本は高度文明国」であるという認識を根底においている。中国文明の影響を受けながらも、独自の一つの文明を成立させているのが日本文明である、と。
従来の見方によれば、日本は「東洋」の一国ということになるのだが、日本は東洋という枠組みにはおさまるものではない。中国文明とは異なる文明である。
そこで、梅棹忠夫が提示したのが「生態史観」という考え方である。文明の発達度合いによって、世界を第一地域、第二地域に分け、西ヨーロッパの数カ国と日本という高度文明国の第一地域とし、それ以外のユーラシア大陸全土を第二地域とした。
ユーラシアでものを考えるための基本的フレームワーク(枠組み)が、「東南アジアの旅から-文明の生態史観・つづき」に収録された2つの概念図である。斜線が引かれた乾燥地帯が、東洋でも西洋でもない「中洋」に該当する。
a図の説明
(出典:「東南アジアの旅から-文明の生態史観つづき」(1958)
b図の説明
(出典:「東南アジアの旅から-文明の生態史観つづき」(1958)
この2つの概念図で明らかなのは、ユーラシア大陸をはさんで反対側に位置している西ヨーロッパと日本が、構造的には同じポジションに位置しているということだ。
つまり、生態学的に地球規模でみれば、第一地域に属する日本と西欧はきわめて似た存在なのであり、そこで発生し発達した「文明」が似通っているのは、ある意味では当然なのである。
梅棹忠夫によれば、文明というものは、自然環境とその社会自体の変化によって起こるものであり、地域により違った発展がありうるのは当然である。これを、生態学用語から転用した「遷移」(succession:サクセッション)という概念でもって説明しているのだが、この発想が、もともと自然科学者から出発した梅棹忠夫の独創的なところなのである。
『文明の生態史観』が発表されてから約40年後に書かれた『文明の生態史観はいま』(梅棹忠夫、中公叢書、2001)で、梅棹忠夫は、この概念図について、どのような発想のもとに作製されたのか、歴史学者の川勝平太との対談みずから語っているので引用しておこう。
あれは気候学をベースにしているんです。気候学の基本概念には「理想大陸」というものがあります。たとえば北半球の大陸では、地球自転の影響で偏西風がおこり、それが地球自転の偏向力によって北へ曲がるのです。その結果、理想大陸の中央には乾燥地帯が斜めに走る。この図ではトポロジー(位相幾何学)の関係性を図にする手法を用いており、あえて距離や方向性については捨象してあります。
・・(中略)・・
もうひとつ、やはり『文明の生態史観』には書いていませんが、そのベースにあるのはケッペンの精密な気候区分なんです。森林の樹種をタイプ分類すると、西ヨーロッパは硬葉樹林のゾーンで、日本は照葉樹林のゾーンになる。これは対応します。
・・(中略)・・
そうなんです、生態史観の基本には、地球幾何学があるんです。その美しさが文科の人にはわかってもらえない。世界文明というものは合理的にできているのです。それは地球の構造からきているわけです。
(出典:『文明の生態史観はいま』 P.42~44)
(ケッペンの気候区分 wikipediaより)
基本的には「中洋」の発見ということがもっとも大きなポイントであると書いたが、これについては、梅棹忠夫も編集委員の一人に名をつらねて、最終巻の『人類の未来』を書く予定であった河出書房版の『世界の歴史 19 インドと中近東』というタイトルに注目していただきいたい。
 インドは、梅棹忠夫が『文明の生態史観』で指摘したように、そこは西洋でも東洋でもない「中洋」としかいいようのない世界なのだ。日本や中国、韓国をふくんだ東アジア世界とはまったく異質の世界である。
インドは、梅棹忠夫が『文明の生態史観』で指摘したように、そこは西洋でも東洋でもない「中洋」としかいいようのない世界なのだ。日本や中国、韓国をふくんだ東アジア世界とはまったく異質の世界である。「インド世界」はむしろその西側に位置する、いわゆる中近東に近いことは、歴史をみれば明らかなのである。その意味では、現在にいたるまで『世界の歴史 19 インドと中近東』(岩村忍・勝藤猛・近藤治、河出文庫、1990)の価値は減じてない。これもまた、東洋学をベースにした「京大歴史学」の成果である。
文庫版のカバーの左側にある、かの有名なタージ・マハールはムガル帝国の皇帝が建設させたものだが、ムガル帝国はイスラーム王朝であり、しかも公用語はペルシア語であったのだ!
文庫版は現在でも入集可能なので、機会があればぜひ手にとっていただきたい歴史書である。
インドを考える際には、英国の植民地となる以前、ムスリム帝国であったムガール帝国が長く支配していた歴史的経緯を考えれば、「中洋」という枠組みで考えたほうがしっくりといくはずなのだが。ちなみに、ムガール帝国の公用語はペルシア語であったことは、世界史で大学受験をする受験生にとっても、盲点の知識かもしれない。
なおインド西部には、イスラーム化されたイラン(=ペルシア)から、ゾロアスター教徒が逃れてきてコミュニティを形成している。パルシーと呼ばれる民族集団である。
 梅棹忠夫が提唱した「中洋」という文明地域概念であるが、かならずしも一般化しているとはいいがたい。
梅棹忠夫が提唱した「中洋」という文明地域概念であるが、かならずしも一般化しているとはいいがたい。国会図書館のデータベースで「中洋」をタイトルに含む本を検索してみても、『文明の生態史観』を収録した『梅棹忠夫著作集 第4巻』(石毛直道ほか編、中央公論社、1990)を除いては、『中洋の商人たち-インド・ペルシャ・アラブの商才民族-』(日本経済新聞社 編、日本経済新聞社、1982)くらいしか見つからない。『中洋の歴史と文化-杉勇古代オリエント学論集-』(杉勇、筑摩書房、1991)という本もあるが、これは専門研究者の専門論文集であろう。
「新興国」として中国とならんで話題になることの多いインドであるが、『中洋の商人たち』という新聞連載をもとにした書籍を出版している日本経済新聞じたいが、「中洋」というコトバと概念をすっかり忘れてしまっているようである。
梅棹忠夫が、最晩年に残したコトバを引用しておきたい。
梅棹 「文明の生態史観」は、少なくともアジアとヨーロッパの両方が見えていて、ちゃんとわかっていないと理解できないと思う。わたしは若いとき、学生時代から、いまの東方文化研究所、東洋学センターの流れのなかにはいっている。・・(中略)・・「文明の生態史観」も東洋学のなかに入っていると思ったらいいやろうな。そして、名前のとおり「生態学」。生態学という流れを理解してほしい。・・(中略)・・そう、みな「生態」がぬけてしまっている。とくに生態史観の基本になっているのはサクセッション理論、これは歴史論なんです。・・(後略)・・
(出典:『梅棹忠夫語る』P.34~36
(特別展「ウメサオタダオ展」 の図録 『知的先覚者の軌跡』(2011年)より )
■「日本はアジアではない」(梅棹忠夫) 日本は「海洋国家」である
梅棹忠夫は、『文明の生態史観』で、日本と西ヨーロッパが文明として対応する関係にあるとしたが、「西欧文明」はさらに「海洋文明」と「大陸文明」に区分しなくてはならない。この両者は、まったく異なる文明のタイプである。
ユーラシア大陸をはさんだ日本と英国とのポジションの近似性について考えることが必要だろう。日露戦争前に、なぜ「日英同盟」が成立したのか、これは政治だけでは理解できないことだ。地球儀を回してみることではじめて理解できることである。
これについては、梅棹理論の創造的発展となった歴史家・川勝平太の『文明の海洋史観』(中公叢書、1997)に言及しなくてはならない。
英国が大陸ヨーロッパではないのと同様、日本はアジアではないのである!!
このことは、 書評 『日本文明圏の覚醒』(古田博司、筑摩書房、2010) でも詳しく書いたが、いまだ日本人の常識となってないのが残念なことだ。
日本と大陸の距離よりも、英国と大陸の距離のほうが短いので、英国はより大陸の影響を受けているのであるが、それでも地政学的にみて日本と英国がきわめて似たポジションにあることは、梅棹忠夫と同時代人であった京都大学教授・高坂正堯(こうさか・まさたか)の『海洋国家日本の構想』を読めば、納得できることだ。書評 『海洋国家日本の構想』(高坂正堯、中公クラシックス、2008) を参照。
たしかに、アングロサクソン世界の衰退が始まっており、海洋国家・米国を中心にしたアングロサクソン世界の重要なメンバーとして国際社会のなかで生きてきた日本は、今後の進路について思考停止状態になっていけないことは言うまでもない。
しかし、新興国と呼ばれる中国もインドもしばらくは勃興するが、ふたたびユーラシア大陸の動乱に巻き込まれて没落していくことも否定できないことだ。いまこれを書いているわたしが生きているあだは、中国やインドはさらに成長するであろうとしても、その後については衰退は必至であろう。
文明の中心は移動するだけなのだ。この重要な教訓は、地球レベルで生態学的に考える「生態史観」からは、当然のように導き出される結論である。
なお、日本と英国の比較については、梅棹忠夫の理論とはまったく独立に英国側から行われた『イギリスと日本-マルサスの罠から近代への跳躍-』(アラン・マクファーレン、船曳建夫監訳、北川文美/工藤正子/山下淑美訳、新曜社、2001)という大著がある。
まだこの本は読んでいないので、ここではコメントはできないが、歴史人類学の立場から、同じ島国という生態系が、同じような文明を生み出してきたことを解明したものである。近い将来、一読してコメントを書いてみたいと思っているのだが・・・。
■文庫版裏表紙に記された小松左京のコトバ
最後に、梅棹忠夫とは同じ関西人で盟友でもあった小松左京の『文明の生態史観』評を引用して、この記事の締めとしたい。文庫版の裏表紙に記されている文章である。
『文明の生態史観』は、戦後提出された最も重要な「世界史モデル」の一つであろう。それは、これまで東と西、アジア対ヨーロッパという、慣習的な座標軸の中に捉えられてきた世界史に革命的といっていいほどの新しい視野をもたらした。この視野によって複雑に対立し、からみ合う世界の各地域の文明が、はじめてその、「生きた現実」の多様性を保ったまま、統一的に整理される手がかりが与えられたといっていい。発表後数年を経てなお色あせぬのみか、将来、一層みのり多い成果が、この視野からもたらされるであろうと期待している。(小松左京、1974年発行の中公文庫版初版)
この「予言」は、そのコトバとおりに実現した。さすが、SF作家であり未来学的な著作も多い小松左京氏ならではの評言であろう。小松左京もまた今年2011年に亡くなったのは残念である。
(画像をクリック!)
PS 画像を一枚追加した(2014年3月27日 記す)。
<ブログ内関連記事>
書評 『「東洋的専制主義」論の今日性-還ってきたウィットフォーゲル-』(湯浅赳男、新評論、2007)-奇しくも同じ1957年に梅棹忠夫とほぼ同じ結論に達したウィットフォーゲルの理論が重要だ
■長期的スパンで歴史を読むために
書評 『日本文明圏の覚醒』(古田博司、筑摩書房、2010)
・・ブローデルの日本の封建制にかんする発言は、自然科学から出発した梅棹忠夫が提唱した「文明の生態史観」と一致している。ブローデルの発想も自然地理学からのものであることは大きな意味をもっていると考えてよいのではないか
「500年単位」で歴史を考える-『クアトロ・ラガッツィ』(若桑みどり)を読む
書評 『1492 西欧文明の世界支配 』(ジャック・アタリ、斎藤広信訳、ちくま学芸文庫、2009 原著1991)
書評 『100年予測-世界最強のインテリジェンス企業が示す未来覇権地図-』(ジョージ・フリードマン、櫻井祐子訳、早川書房、2009)
・・1492年にはじまった西欧500年の支配史は1991年のソ連崩壊によって終わる
書評 『歴史入門』 (フェルナン・ブローデル、金塚貞文訳、中公文庫、2009)・・封建制が西欧と日本だけのものであることも指摘
『ソビエト帝国の崩壊』の登場から30年、1991年のソ連崩壊から20年目の本日、この場を借りて今年逝去された小室直樹氏の死をあらためて悼む
書評 『ヨーロッパとは何か』(増田四郎、岩波新書、1967)
書評 『失われた歴史-イスラームの科学・思想・芸術が近代文明をつくった-』(マイケル・ハミルトン・モーガン、北沢方邦訳、平凡社、2010)
「想定外」などクチにするな!-こういうときだからこそ、通常より長いスパンでものを考えることが重要だ
「理科のリテラシー」はサバイバルツール-まずは高校の「地学」からはじめよう!
■海洋国家としての日本
書評 『海洋国家日本の構想』(高坂正堯、中公クラシックス、2008)
・・通商国家日本の生存条件について書かれた戦後日本の古典的名著。梅棹忠夫とともに戦後日本の論壇をリードした京大の知性
書評 『日本は世界4位の海洋大国』(山田吉彦、講談社+α新書、2010)
書評 『平成海防論-国難は海からやってくる-』(富坂 聰、新潮社、2009)
海上自衛隊・下総航空基地開設51周年記念行事にいってきた(2010年10月3日)
マンガ 『沈黙の艦隊』(かわぐちかいじ、講談社漫画文庫、1998) 全16巻 を一気読み
書評 『江戸時代のロビンソン-七つの漂流譚-』(岩尾龍太郎、新潮文庫、2009)
(海洋国家としての英国)
書評 『大英帝国衰亡史』(中西輝政、PHP文庫、2004 初版単行本 1997)
書評 『「海洋国家」日本の戦後史』(宮城大蔵、ちくま新書、2008)
書評 『田中角栄 封じられた資源戦略-石油、ウラン、そしてアメリカとの闘い-』(山岡淳一郎、草思社、2009)
■「封建制」について
書評 『歴史入門』 (フェルナン・ブローデル、金塚貞文訳、中公文庫、2009)
書評 『日本文明圏の覚醒』(古田博司、筑摩書房、2010)
・・ブローデルの日本の封建制にかんする発言は、自然科学から出発した梅棹忠夫が提唱した「文明の生態史観」と一致している。ブローデルの発想も自然地理学からのものであることは大きな意味をもっていると考えてよいのではないか
書評 『封建制の文明史観-近代化をもたらした歴史の遺産-』(今谷明、PHP新書、2008)-「封建制」があったからこそ日本は近代化した!
書評 『日本近代史の総括-日本人とユダヤ人、民族の地政学と精神分析-』(湯浅赳男、新評論、2000)-日本と日本人は近代世界をどう生きてきたか、生きていくべきか?
書評 『革新幻想の戦後史』(竹内洋、中央公論新社、2011)-教育社会学者が「自分史」として語る「革新幻想」時代の「戦後日本」論
■ユーラシア大陸国家の興亡-海洋国家・日本の反面教師
書評 『モンゴル帝国と長いその後(興亡の世界史09)』(杉山正明、講談社、2008)
・・大陸国家の本質について考えることは、それとは全く異なる生存条件をもつ海洋国家・日本について考えるための合わせ鏡となる
書評 『帝国陸軍 見果てぬ「防共回廊」-機密公電が明かす、戦前日本のユーラシア戦略-』(関岡英之、祥伝社、2010)
『ソビエト帝国の崩壊』の登場から30年、1991年のソ連崩壊から20年目の本日、この場を借りて今年逝去された小室直樹氏の死をあらためて悼む
書評 『ノモンハン戦争-モンゴルと満洲国-』(田中克彦、岩波新書、2009)
■地球の法則
「理科のリテラシー」はサバイバルツール-まずは高校の「地学」からはじめよう!
・・地学とは地球科学の略。地学の知識は現代人の教養であるべき
書評 『ああ正負の法則』(美輪明宏、PARCO出版、2002)-「正負の法則」は地球の法則である
・・地球が自転しているから、地軸が傾いているから、地球には昼夜の区別があり、四季がある
■梅棹忠夫関連
書評 『梅棹忠夫 語る』(小山修三 聞き手、日経プレミアシリーズ、2010)
・・最晩年の放談集。日本人に勇気を与える元気のでるコトバの数々
書評 『梅棹忠夫のことば wisdom for the future』(小長谷有紀=編、河出書房新社、2011)
書評 『梅棹忠夫-地球時代の知の巨人-(KAWADE夢ムック 文藝別冊)』(河出書房新社、2011)
書評 『梅棹忠夫-知的先覚者の軌跡-』(特別展「ウメサオタダオ展」実行委員会=編集、小長谷有紀=責任編集、千里文化財団、2011)
梅棹忠夫の幻の名著 『世界の歴史 25 人類の未来』 (河出書房、未刊) の目次をみながら考える
『東南アジア紀行 上下』(梅棹忠夫、中公文庫、1979 単行本初版 1964) は、"移動図書館" 実行の成果!-梅棹式 "アタマの引き出し" の作り方の実践でもある
書評 『回想のモンゴル』(梅棹忠夫、中公文庫、2011 初版 1991)-ウメサオタダオの原点はモンゴルにあった!
書評 『人間にとって科学とはなにか』(湯川秀樹・梅棹忠夫、中公クラシック、2012 初版 1967)-「問い」そのものに意味がある骨太の科学論
梅棹忠夫の幻の名著 『日本探検』(1960年)が、単行本未収録の作品も含めて 2014年9月 ついに文庫化!
(2014年10月30日、2016年1月20日 情報追加)
(2023年11月25日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年12月23日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年6月24日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年11月19日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年10月22日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2020年12月18日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2012年7月3日発売の拙著です 画像をクリック!)
end