 『大砲と帆船』というタイトル
『大砲と帆船』というタイトルはきわめて簡潔だ。だが、それだけではない。
タイトルがすべてを物語っているのである。
英語の原題は Guns, Sails, and Empires: Technological Innovation and Early Phases of European Expansion, 1400 - 1700 直訳すれば、『大砲、帆船、帝国-技術イノベーションとヨーロッパ拡大の初期段階』となる。これでは長すぎる。日本語タイトルは、ギリギリまで切り詰めており秀逸だ。
「大砲と帆船」の組み合わせが、近世(=初期近代)以降の「海上」におけるヨーロッパの優位性を作り出したのである。
戦争に使用される大砲と、海上移動に使用される帆船は、それぞれ別個に発達したテクノロジーだが、この2つが結びついたことで、足し算以上の掛け算としての威力を発揮することになったのだ。
要は、機動力と破壊力である。陸上の戦闘で城塞を攻撃するための大砲の効果は大きいが、いかんせん大砲を戦場まで移動させることは大きな問題であった。この問題を解決したのは、大砲を帆船に搭載することで実現し、以後この組み合わせの技術進歩が休むことなく続いている。
風を動力とする帆船の時代が終わり、石炭を燃料とする蒸気船の時代になっても、石油を燃料とする時代になっても、技術進化の方向に変化はない。軍事的な覇権がヨーロッパから米国にシフトして以降も、本質に変化はない。
もちろん、航空兵力と潜水艦の発展によって、「大艦巨砲主義」の時代が終わったことを痛切に感じさせられたのは、大東亜戦争で戦艦大和を失った日本と日本人であったことは、あえて書くまでもあるまい
■ヨーロッパによる世界覇権の第一歩は「海上」の「大砲と帆船」でもたらされた
「海上」でフルに発揮されたヨーロッパの優位性は、「陸上」では十分に発揮されなかった。これは本書のなかでは、もっとも興味深い指摘である。
アメリカ大陸に支配を及ぼしたヨーロッパ勢力だが、アジアにおいては(アフリカにおいても)、かなり長期にわたって沿岸地域しか確保できなかったのはそのためだ。ここでいうアジアとは東アジアのことであろう。端的にいって、中国と日本のことである。
ポルトガルが確保したのは、ゴアやマラッカ、そしてマカオという「点と線」であり、後発組のオランダもまたそれをなぞったに過ぎない。内陸まで侵攻するようになったのは、19世紀後半の英国によるインド植民地化以降のことだ。
本書では言及されていないが、ヨーロッパ勢力が「陸上」で優勢性を発揮できなかった典型的な例は「島原の乱」(1637~38)であるといっていいだろう。逆に、日本が「海上」で優位性をもつヨーロッパ勢力と組まなかったため、大いに苦労したのが「朝鮮之役」(1592~1598)であろう。
以下、「島原の乱」と「朝鮮之役」(・・日本で一般的な「文禄・慶長の役」のこと)について、「海上」の優位性という観点から整理しておこう。まずは時間的に先行する「朝鮮之役」から始める。
「朝鮮之役」にかんしては、「大砲と帆船」を用意できなかったための問題点も浮上している。
そもそも秀吉の構想は中国征服が目的であったわけで、島国の日本が中国に向かうには朝鮮半島に上陸するのがいちばん近道である。戦争においては将兵と武器弾薬、それに糧食も含めた物資を輸送するためのロジスティクスが必要である。まずは、渡海のための船が必要である。これは日本水軍が担っていた。
だが、「海上」での戦闘を主目的にしていたわけではなく、あくまでも人員と物資を無事に上陸させることに主眼点がおかれていたわけである。もちろん、使用された安宅船には火縄銃式の大鉄砲が備え付けられていた。
「海上」の戦闘においては、敵の船に接舷して切り込んでゆく白兵戦指向で、この点においては当時の日本軍は無双の強さを誇っていた。後述するように、同時代の地中海のガレー船による戦いもまた同様であった。
とはいえ、朝鮮水軍の李舜臣に翻弄されるといった事態も発生している。李舜臣と亀甲船については過大評価のきらいがあるものの、出兵準備の段階でポルトガルなりスペインの大砲積載船を確保できていれば、朝鮮水軍は簡単に撃破できていたはずだ。だが、秀吉にはいまひとつ戦略眼が欠けていたのか、それ以上に反キリシタン意識が強かったのか、そうはならなかった。
話を元に戻そう。「海上」はさておき、「陸上」において大砲が使用される可能性は、大坂の陣以降の日本ではすでに低くなっていた。
「島原の乱」においては、「立ち返りキリシタン」を中心とした一揆勢力は、キリシタン浪人たちの指導のもと、島原湾に面した原城に籠城することになる。そこで幕府は、オランダ東インド会社(VOC)に命じて、帆船軍艦の大砲で原城を攻撃させたのであった。幕府には、大砲を積載した船がなかったからだ。
実質的に「家臣」となっていたプロテスタント勢力のオランダに命じたのである。キリシタン勢力のバックには、カトリック勢力のポルトガルがいると幕府は睨んでいた。この意味では、ヨーロッパにおける宗教戦争が島原の地で展開されたと見なすことも可能だ。
18世紀オランダの政治家ファン・ハーレンが書いたオランダ弁護の書『日本論-日本キリシタンとオランダ』(筑摩書房、1982)によれば、VOCは軍艦1隻を差し向け、15日間で合計425発の砲弾を発射している。このときの船の積載砲は26門で、6門が12ポンド砲、残りが6ポンド砲であった。だが、ほぼ水平方向にしか撃てない艦載砲では、実際にはあまり効果がなかったようだ。
砲撃では重大な損傷をもたらしていないどころか、城からの銃撃でオランダ兵が殺されている。その後、幕府はオランダに依頼して臼砲の製造を行わせた。幕府への献上品として、将軍家光の御前で試射が行われたが、かならずしも思うような結果が出なかったらしい。
島原の乱の集結後に幕府はポルトガル船の来航を禁止し断交したが、当然のことながらポルトガルの反撃を想定していた。実際にはポルトガルは反撃してくるどころか、マカオから貿易再開を哀願してだけであった。幕府は、ポルトガル使節を無慈悲にも斬り捨てている。絶対に勝てるという自信があったのだろう。
戦国時代(16~17世紀)の日本は、陸戦でモノをいう火縄銃の開発と量産には注力していたが、大砲はあくまでも補助的な位置づけにしていたようだ。
秀吉の「朝鮮之役」では明軍のフランキ砲という大砲に苦戦したにもかかわらず(とはいえ、日本軍の小銃と槍の組み合わせで明軍を圧倒している)、家康は関ヶ原の戦いでも、大坂の陣でも、大砲は補助的な役割しか与えていない。しかも使用したのはイングランド製なりオランダ製の輸入品だ。国内で量産化され普及していた火縄銃と違って、大砲は西欧から輸入すればいいとみなしていたようだ。
21世紀の現在では想像しにくいが、日本のみならずヨーロッパにおいても、道は舗装されていなかったことを考えれば、大砲の移動が容易ではなかったことが理解できるだろう。
古代ローマでは街道は石で舗装されていたが、それ以外の地域では舗装道路は存在しなかった。現在では標準のアスファルト舗装が誕生したのは19世紀前半の英国である。
(付注)日本最初の艦砲射撃は「門司城の戦い」(1561年)に行われている。毛利家に奪われた門司城の奪還を目指したキリシタン大名の大友宗麟は、博多に停泊していたポルトガル船に艦砲射撃を行わせたといわれる。だが、勝敗を決するような砲撃ではなかったようで、ついに門司城の奪還は叶わなかった。もっとも有名な艦砲射撃は、薩英戦争(1863年)における英海軍による鹿児島城下焼き払いであろう。だが、戦いそのものは互角であり、英海軍の司令官が薩摩側の砲撃によって戦死している。
■「大砲」の発達
「大砲と帆船」が西欧の優位性を生み出したわけであるが、その発達史を大砲と帆船にわけて、本書以外の文献も参考にしながら簡単に整理しておこう。
そもそも火砲はヨーロッパで生まれたのではなく、中国で生まれたものである。これはすでに常識だといっていいだろう。
かつては、印刷術・火薬・羅針盤が「ルネサンスの三大発明」といわれたこともあったが、これは無知にもとづく西欧中心主義の妄想であったというべきだろう。21世紀の現在、このような表現はもはや通用しない。
では火砲はいかにしてヨーロッパに伝来したのか? それは、13世紀のモンゴル帝国の成立によるものだ。モンゴルが東方から西方に軍事的に拡大していった時期、遊牧民のモンゴル軍は中国人の火砲技術者を連れて陸路でユーラシアを縦断していったのである。モンゴル軍は国際混成部隊であった。
あわや西欧社会はモンゴルの手に落ちるかという瀬戸際で、偶然的な事象の発生でモンゴル軍が撤退したのだが、ポーランドからハンガリーにかけてまでモンゴルに征服されている。ロシアは長期にわたってモンゴルの支配下にあった。
中国からヨーロッパに伝来した火砲は、ヨーロッパで独自の発展を遂げるようになる。同時に中国においても独自の発展を遂げていった。14世紀の寒冷化のなか中国の支配者は元から明に代わるが、明軍が火砲を使用していた。だが、社会が安定するにしたがい、明朝は火砲の使用を制限するようになった。
ヨーロッパでは、火砲は城塞攻撃の武器として重用されるようになる。有名な15世紀前半に活躍したジャンヌ・ダルクは、騎士がいやがる大砲を積極的に使用し、砲兵隊を独立させている。だが、火砲をもっとも効果的に使用したのは、オスマン帝国によるコンスタンティノープルの陥落(1453年)であろう。
ところが、16世紀の初めには火縄銃が発明され、小銃中心の時代となり、大砲の技術開発は後回しとなった。火縄銃が種子島に伝来したのは16世紀半ばのことだ。小銃の製造は当時の技術水準からみて手頃なものだったので、ヨーロッパだけではなく日本でも爆発的に普及することになる。以後、16世紀は火縄銃と槍の組み合わせが戦闘の標準形となったのは、ヨーロッパも日本もおなじである。
面白いことに、中国には16世紀の始めにヨーロッパ製の大砲も小銃も伝来していたが、大砲はフランキ砲という形で導入されたが、小銃は普及しなかった。16世紀から17世紀にかけての、大砲志向の中国と小銃志向の日本との違いが興味深い。
素材と材料という観点から大砲について見てみると、ヨーロッパでは最初は青銅製が中心であった。銅と錫の合金である青銅(ブロンズ)は、加工しやすいというのが最大の利点であったが、材料費が高いのでコスト高になるのが難点であった。青銅製の大砲製造の中心は、先進地帯のフランドル地方であった。
青銅に対して、加工はしにくいがコストが低いのが鉄である。鉄製の大砲の技術革新を行ったのがイングランドである。経済後進国ではあったが、イングランドには豊富な鉄鉱石があったためだ。余談だが、18世紀の後半には、原材料の鉄鉱石に加えて燃料としての石炭にも注目が集まり、その双方を産出するイングランド(英国)で世界最初の「産業革命」が始まることになる。
17世紀は「オランダの黄金時代」であったが、オランダはスペインからの独立戦争を戦う必要から大砲を必要としていた。アジア海域では、先行する競合先ポルトガルやスペインの勢力に対応するため掠奪を中心に活動を行っていた。そのため、帆船に大砲を積載することが必要であり、大きな需要が生じていた。
オランダはイングランドから輸入していたが、後背地ともいうべきドイツやスウェーデンに目をつけることになる。豊富な鉱物資源を有するスウェーデンは、旺盛なオランダの需要に応えるべく大砲の一大生産国となっていく。
銅の産出国であるスウェーデンでは、最初は青銅製が中心だっが、鉄鉱石も豊富に産出することもあり、コスト安の鉄製大砲を求めるオランダの需要の応えて、鉄製大砲の主要生産国となっていった。現在までつづく兵器製造大国スウェーデンは17世紀半ばに誕生したのである。
「大砲と帆船」というテーマでいえば、青銅製であれ鉄製であれ、帆船に積載されることで機動力を確保し、遠距離航海が可能になることで、軍事力の裏付けをもった経済進出を可能とするようになったのである。
■「帆船」がメインになる
現在のように動力が石油になる以前は、船の動力が人力や風力に頼るのは、世界中どこでも当たり前であった。
自然界に存在する風力を利用した帆船は、ある意味では人類史とともに存在する。中国のジャンク、インド洋のダウ船は、いずれも帆船である。
だが、帆船の技術が高度に発達したのは西欧である。14世紀の1本マストから15世紀には2本マストに発展し、その後は3本マストで5枚から6枚の帆をもつ全装帆船へと発達していく。
古代文明の中心の1つであった地中海世界では、帆船ではなくガレー船が中心であった。水深が深くて干満差がほとんどなく、波が比較的穏やかだが、風向きが不安定で突風もあるため、人間が漕ぐ人力のガレー船が適していたのである。
イタリアの都市国家ヴェネツィア、ジェノヴァの商船、スペインの商船と艦船もまたガレー船であった。ヨーロッパのキリスト教勢力が初めてイスラーム勢力を破った「レパントの戦い」(1571年)は、ガレー船の絶頂期であった。
ところが、地中海からジブラルタルを出て大西洋、さらに北海に入るとガレー船では対応できなくなる。というのは、北海は水深が浅くて干満差が大きく、特に冬場は荒天が続いてウネリも大きく、一部では結氷もある。だが、洋上では風向きが季節によって一定しているので風力を利用する帆船が適していたのであった。
南の地中海と北の北海でそれぞれ発達してきた造船技術が融合することで、15世紀にはヨーロッパの帆船技術は飛躍的に進歩することになった。この時代に、いわゆる「大航海時代」を先導して大西洋からアフリカ、さらにはアジアまで進出していったのがポルトガルだ。
この動きはおなじカトリック国であったスペインも追随することになる。さらにはプロテスタント勢力もオランダとイングランドが続いていくことになった。
PS イタリア人の著者が最初から英語で書いた本
著者のカルロ・M・チポラ(Carlo Maria Cipolla、1922~2000)はイタリアの経済史家。『時計と文化』など、もっぱら英語で科学史と経済史の双方にかかわる分野で旺盛な執筆を行った人だ。
『大砲と帆船』は、さらに軍事史にもかかわるテーマであり、簡潔な記述の背後には膨大な研究蓄積があることが、著者による詳細な注で明らかだ。
第2次世界大戦後の世界には、イタリア人が英語で作品を発表するようになった。カルロ・チポラ教授もそうだし、『ロミオとジュリエット』や『ブラザー・サン シスター・ムーン』の監督でオペラ演出家のフランコ・ゼフィレッリ(1923~2019)もそうだった。ほとんどの映画作品は英語である。
2人は同世代である。もともと英語が得意だったということもあろうが、1943年のイタリアの敗戦時で20歳だったという世代であったことも影響しているのだろう。
おなじ敗戦国とはいえ、人口が1億人台の日本と違って、人口6000万人程度のイタリア人の作家にとって、最初から英語で作品を問うという路線が成功をもたらしたことは間違いない。英語でなければ世界の頂点には立てない、そういう時代となっている。
ある意味では、きわめて現実的な選択であったといえよう。
<ブログ内関連記事>
・・17世紀の「オランダの黄金時代」は造船技術によってもたらされた
・・西欧の覇権は、海の利用によってもたらされた
・・17世紀前半のスウェーデンが「三十年戦争」でイニシアティブを握ったのは、クリス的な女王の父グスタフ=アドルフであった。彼は機動的な野戦砲を導入しただけでなく、「16世紀オランダ軍事革命」の申し子でもあった
・・幕末の19世紀半ばに鉄製大砲を鋳造するための最先端の製鉄炉が反射炉だった
・・幕末に至るまで日本は小銃志向の強い国であった
・・このカタログには大砲はほんの少ししか登場しない。あるのはロケットランチャーのような大筒だけだ
(2022年12月23日発売の拙著です)
(2022年6月24日発売の拙著です)
(2021年11月19日発売の拙著です)
(2021年10月22日発売の拙著です)
(2020年12月18日発売の拙著です)
(2020年5月28日発売の拙著です)
(2019年4月27日発売の拙著です)
(2017年5月18日発売の拙著です)
(2012年7月3日発売の拙著です)
ケン・マネジメントのウェブサイトは
ご意見・ご感想・ご質問は ken@kensatoken.com にどうぞ。
お手数ですが、クリック&ペーストでお願いします。
禁無断転載!
end







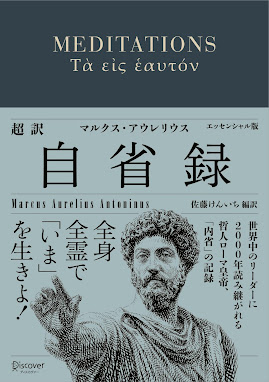


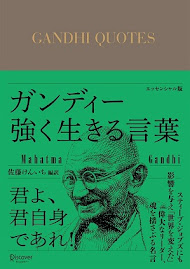











.png)






