先日のことだが、『パステルナーク事件と戦後日本-「ドクトル・ジバゴ」の苦難と栄光』(陶山幾朗、恵雅堂出版、2019)という本を読んで、たいへん充実した読後感を抱いた。 1958年の「パステルナーク事件」という知られざる事件にまつわる日本の知識階層の精神風景を描いたものだ。
パステルナークはソ連時代に生きたロシアの詩人。ロシア革命とその後に続いた内戦を舞台にしたヒューマン・ドラマの映画『ドクトル・ジバゴ』(1965年)の原作者である(*現在に至るまで原作を読む機会がないのが残念だ。映画のほうはなんども繰り返し見ているのだが・・)
そのパステルナークが心血を注いで完成させたものの、当時のソ連では出版できなかった大河小説『ドクトルジバゴ』が、1957年にイタリアで出版されたことに始まるのが「パステルナーク事件」(1958年)だ。 当時すでに「ハンガリー動乱(あるいは革命)」(1956年)によって、ソ連と共産主義への支持に陰りが見え始めていた時期である。
そのパステルナークが心血を注いで完成させたものの、当時のソ連では出版できなかった大河小説『ドクトルジバゴ』が、1957年にイタリアで出版されたことに始まるのが「パステルナーク事件」(1958年)だ。 当時すでに「ハンガリー動乱(あるいは革命)」(1956年)によって、ソ連と共産主義への支持に陰りが見え始めていた時期である。
1958年度のノーベル文学賞が、パステルナークに授与されることが発表され詩人が受諾したにもかかわらず、わずか1週間で辞退するに至った。ソ連の体制側からの激しい誹謗中傷と圧力がかかったからである。ロシアにとどまりたかった詩人は、受賞を断念することを余儀なくされた。本書の記述を読めば、それはもう、すさまじいの一言に尽きる。これが第3章までの内容だ。
このうような「パステルナーク事件」について、世界中の文学者たちから「表現の自由」を守れとして大きな非難が起こったのだが、日本のペンクラブではかならずしもそうではなかった。
日本国内と日本以外では、温度差の違いと要約できるもの以上のものがあったこと、「1958年の日本の知識階層の精神風景」を綿密に描き出したのがこの著作である。
戦前の挫折した社会主義運動という屈折した前史をもつ、この特殊ともいえる「1958年の日本の知識階層の精神風景」をあぶり出すことになったのが、日本ペンクラブの外国人会員であった米国人の日本文学研究者で『源氏物語』の英訳者である)エドワード・サイデンステッカーによる異議申し立てであり、ちょうどその頃に来日した著作家のアーサー・ケストラーであった。
1958年は、反米ナショナリズムが燃えさかった「60年安保」の前夜であり、当時の日本ではアメリカの大衆文化が圧倒的な影響力をもちながらも、同時に反米意識がかなり強く存在した時代だ。そんな時代に、米国人からの異議申し立てに対して左翼的傾向の強い文学者たちが、どのような反応を示したかというと、現在では想像するのも難しい。
さらにいえば、もともと熱心な共産党員であったが、その後共産党と縁を切った経験をもつケストラーにとって、日本の文学者たちの姿勢は当然容認できるようなものではなかったのである。ケストラーの『真昼の暗黒』(1940年)は、そんなソ連の体制を徹底批判して世界的ベストセラーになっている。
冷戦時代のソ連、そして日本。獲得形質は遺伝するとしてソ連で公認されていたルイセンコ学説をめぐる興亡。せっかく著作家ケストラーとルイセンコ学説の双方を別個に取り上げながら、ケストラーの『サンバガエルの謎』(1971年)に触れなかったのは、画竜点睛を欠くというか、ちょっと残念だったような気もする。だが、こんな内容を400ページのボリュームでまとめたこの著作は、じつに充実した内容で読みごたえがあった。
驚いたことに、著者の陶山幾朗氏は、なんと『パステルナーク事件と戦後日本-「ドクトル・ジバゴ」の苦難と栄光』の出版直前に78歳で急逝されていたらしい。「刊行への経緯」に記されている。だから。この本が文字通りの遺作となったことになる。
それにしても、素晴らしい内容の著作を残していただいたものである。万人向けの本でないが、このテーマに関心のある人は、読んでけっして損のない本であると言っておきたい。
目 次序章 発端-1958年10月23日第1章 祝福から迫害へ-1958年10月23日~11月6日第2章 「事件」前史-1956~58年第3章 日本語版『ドクトル・ジバゴ』狂騒曲第4章 糾弾者エドワード・サイデンステッカー第5章 「文士」と政治-高見順(1)第6章 「怖れ」と「美化」と-高見順(2)第7章 「モスクワ芸術座」という事件第8章 《害虫》のポリティクス第9章 “ワルプルギスの夜” の闇第10章 『真昼の暗黒』の来日-アーサー・ケストラー(1)第11章 「目に見えぬ文字」への道程-アーサー・ケストラー(2)第12章 “勝利” の儀式?-第3回ソビエト作家大会(1)第13章 クレムリン宮殿の中野重治-第3回ソビエト作家大会(2)第14章 「事件」の終わり-かくて人びとは去り…補遺わが国メディアに現れた「パステルナーク事件」関連論評(1958~1967)「パステルナーク事件」関連年表跋 天上のことばを、地上にあって 工藤正廣あとがき刊行までの経緯
著者プロフィール陶山幾朗(すやま・いくろう)1940年生まれ。1965年早稲田大学第一文学部卒。著書に『シベリアの思想家ー内村剛介とソルジェニーツィン』(風琳堂)、『内村剛介ロングインタビュー』(恵雅堂出版)、『現代思潮社という閃光』(現代思潮社)、編集『内村剛介著作集』全七巻(恵雅堂出版)。 雑誌『VAV』同人。 2018年11月2日 急逝(78歳)。
(2023年11月25日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年12月23日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年6月24日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年11月19日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年10月22日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2020年12月18日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2012年7月3日発売の拙著です 画像をクリック!)
end






















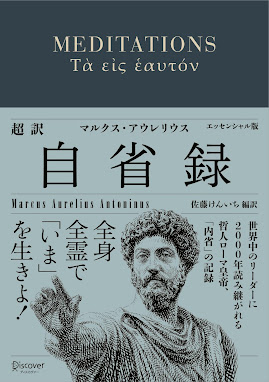


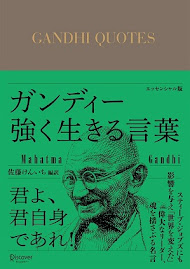











.png)






