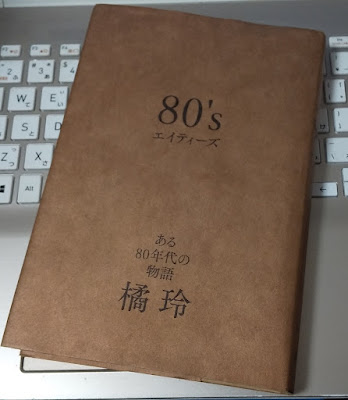『80's エイティーズ ある80年代の物語』(橘玲、太田出版、2018)を読んだ。ベストセラー作家の1980年代の「記憶のなかの物語」。
元「宝島」編集長は1959年生まれ。1962年生まれのわたしとは3年しか違わないので同時代人といっていいと思うが、10代後半から20代前半における3年間の違いはかなり大きなものもある。
「人生はほぼ20歳までの経験で決まってしまう」という英国の作家の発言もある。この本もまた、同時代体験の捉え方の共通点と相違点を興味深く感じながら読んだ。
著者は、「80年代」は「1995年に終わった」としているが、この点にかんしてはまったく同感だ。
1995年は、阪神大震災に始まりオウム事件を体験した年だ。大地震動の時代が始まり、精神世界が前面に浮上してきた年だ。前者はバブル時代の余波への終止符、後者はバブル時代の鬼子として。
たまたま学生時代(1980年代前半)の大学ゼミの写真をさがしてほしいという友人からの依頼を受けて作業していたら、前回の地震で本棚から落ちて転がり落ちていた『80's』というタイトルの本が目に入った。買っていたことすら忘れていたのだった。
不思議な偶然に驚きながら、さっそく読んでみた。偶然の一致(=シンクロニシティ)は夢のなかだけでなく、現実(うつつ)のなかでも起きることなのだな、と。
著者は、あとがきの末尾をこう結んでいる。「振り返ってみれば、バカな頃がいちばん面白かった。だけど、ひとはいつまでもバカではいられない。そういうことなのだろう」 。この実感には、大いにうなづくものを感じる。
1980年代とは、そんな時代だった。
<ブログ内関連記事>
・・「20歳までにその人の人生の大まかなところは決まってしまうと言ったのは、私の記憶ではたしか『長距離走者の孤独』を書いた英国の作家アラン・シリトーのことだったようだ」
(2021年11月28日 情報追加)
(2023年11月25日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年12月23日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年6月24日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年11月19日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年10月22日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2020年12月18日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2012年7月3日発売の拙著です 画像をクリック!)
end