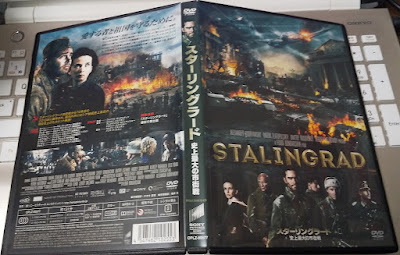『T-34 レジェンド・オブ・ウォー』(2018年、ロシア)という映画を視聴。amazon prime video がやたら推奨してくるので視聴することにした次第。112分。
第2次世界大戦の「独ソ戦」での戦車 vs 戦車のタンクバトル。ドイツの機甲師団に対して孤軍奮闘するソ連のT-34戦車。善戦むなしく、生き残った将兵はすべてドイツの捕虜となる。
だが、数年後に収容所に予期せぬ事態が発生。ドイツ軍が鹵獲(ろかく)したばかりの最新型の T-34を使って、対ソ戦車戦のリアル演習をやるというのだ。このチャンスに捕虜となった少尉がT-34で捕虜収容所を脱出することを密かに計画、実行に踏み切る、という内容の奇想天外の内容。
最初はやや眠気を感じたので、どうかなあとも思ったが、収容所での予期せぬ事態の発生と、その後の展開があまりにテンポがよくて面白すぎるので、最後まで見ることに。もちろん、最近のロシア映画の例に漏れず、砲弾が飛んでくるスローモーションのシーンなど、あまりにもマンガチックなのだが(笑)
ロシアでは、wikipedia情報によれば、「最終興行収入は40億円を超え、観客動員800万人」とのこと。大ヒット作品というわけだ。
(ロシア版ポスター wikipediaロシア語版より)
今年2022年のロシアの「対独戦勝記念日」の軍事パレードにも、リアルT-34が登場していたこともあり(・・70年以上前の戦車を、整備に整備を重ねて現役で動かしているらしい)、ロシア人にとって T-34は「大祖国戦争」とは切っても切り離せないのだな、とあらためて確認。
「愛国作品というものは、なによりもまず娯楽作品でなくてはならない。なぜなら、シリアスな作品など民衆は歓迎されないからだ」という意味の、ナチスの宣伝相ゲッベルス博士の理論を想起するが、まあ、むずかしい話は抜きにして、面白い映画だった。
<ブログ内関連記事>
(2021年11月19日発売の拙著です)
(2021年10月22日発売の拙著です)
(2020年12月18日発売の拙著です)
(2020年5月28日発売の拙著です)
(2019年4月27日発売の拙著です)
(2017年5月18日発売の拙著です)
(2020年5月28日発売の拙著です)
(2019年4月27日発売の拙著です)
(2017年5月18日発売の拙著です)
(2012年7月3日発売の拙著です)
ツイート
ケン・マネジメントのウェブサイトは
ご意見・ご感想・ご質問は ken@kensatoken.com にどうぞ。
禁無断転載!
end
ツイート
ケン・マネジメントのウェブサイトは
ご意見・ご感想・ご質問は ken@kensatoken.com にどうぞ。
お手数ですが、クリック&ペーストでお願いします。
禁無断転載!
end

.png)