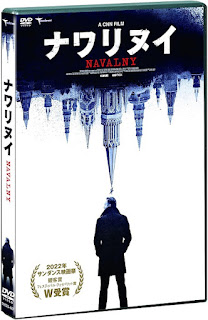『ダブル・フェイス』(2017年、フランス・ドイツ・イスラエル)という映画を amazon prime video で視聴した。なにか面白そうなイスラエル映画でもないかなと amazon で探していたら出てきたのがこの作品だ。93分。
モサドの女工作員と、ヒズボラ幹部の元愛人という協力者。この2人の奇妙な共同生活を描いたもの。基本はスパイスリラーである。
モサドの女工作員の名前はナオミ。日本人っぽい響きだが、これはもともと旧約聖書に登場する女性の名前だ。2年間の病欠状態で、復帰にはちょうどいいだろうということで、「比較的軽い」任務を打診される。
そのミッションは、イスラエルにとっての仇敵・武装組織ヒズボラの幹部の元愛人で、ヒズボラを裏切ってモサドの協力者(インフォーマント)となっていたレバノン人女性を安全な「隠れ家」で保護するというものだ。
協力者は顔を整形されており、2週間たって傷が癒えたら偽装パスポートで第三国のカナダに逃亡させることになっている。そんな作戦の一環である。だが、作戦の詳細はナオミには知らされていない。
モサドがドイツのハンブルクに確保した隠れ家で、ドイツ人に偽装してクラウディアという偽名をつかって暮らすことになる主人公。この2人の奇妙な共同生活は、最初のよそよそしい関係から、じょじょに心を開いていく関係を描いている。2人はともに人には言えない心の傷を抱いていたからだ。
映画の舞台は、ほとんどがドイツ北部のハンブルクで、2人の女性の会話が映画のほとんどを占め、しかも英語で会話がなされている。隠れ家の近隣住民とはドイツ語。モサド工作員が上司としゃべるときはヘブライ語。ヒズボラの幹部と部下たちはアラビア語。
メルケル時代の2015年から「シリア難民」を大量に受け入れていたドイツ社会。それ以前からトルコ系のムスリムが当たり前となっていたが、その状態よりさらにドイツのムスリム化が進んでいるのだろう。
元愛人を探しだし、抹殺する使命を帯びて複数のヒズボラ隊員たちがハンブルク入りしているが、そんな状態のドイツでは、中東系のテロリストが紛れ込んでいても、それほど目立たなくなっているのである。
この映画が製作され公開された2018年は、「自称イスラーム国」(ISIS)の全盛期で、ドイツ国内はテロ警戒レベルが5段階で4まで上昇していた。
ISIS壊滅を狙っていた米国はクルド人を味方につけ、敵対するイランとの裏取引も行っている。レバノンに拠点を置く武装組織ヒズボラの背後にはイランがいるである。そんな背景は、あっという間に過去のものとなってしまい、2023年の現時点ではすでに理解しにくいものとなっている。この映画を見ていて、ようやく思い出したくらいだ。
この2人の奇妙な共同生活は、モサド上層部の判断で突然終わることになる。味方を裏切って敵の協力者となった人間など、情報機関から見たらしょせん駒に過ぎないのか。悲しいものである。
(主人公のナオミ。トレーラーよりキャプチャ)
だが、ナオミの任務はドイツで終わることなく、直接テルアビブには戻らず、さらに違う偽名のパスポートでレバノンに入国、ベイルートでヒズボラ幹部を・・・(ここから先はネタバレになるので記さない)。
■ヨーロッパを舞台にしたモサドもの映画
日本での劇場公開はなく、いきなりDVDが発売されたようだ。アマゾンでのカスタマレビューの評価はあまり高くないが、それはそれなりに楽しめる作品である。ただし、日本人には映画の背景が理解しにくいのが難点であろう。
モサドものといえば、スピールバーグ監督の『ミュンヘン』が有名だが、イスラエルにもモサド映画があるわけだ。それもはるか昔の「伝説のスパイ」を描いたものではない。ごく最近のもので、舞台がヨーロッパとレバノン。
最後の最後で、主人公のモサド工作員が職員としての継続勤務を拒否するにいたる点は、男性と女性の違いはあっても『ミュンヘン』とおなじである。ただし、『ダブル・フェイス』のほうは、限りなくフィクションであろう。
映画を見ていて思うのは、日本など外国での評価と違って、どうやらイスラエル本国ではモサドの評価はかならずしも高くないようだ。等身大の描き方だといえば褒めたことになるが、すくなくともモサド礼賛とはほど遠い。
日本版の『ダブル・フェイス』となっているが、英語版のタイトルは『Shelter』となっている。「シェルター」は「隠れ家」という意味だが、内容的からみたら日本版のタイトルのほうがすぐれている。整形前と整形後の2つの顔。モサド工作員と協力者の2つの顔。だからダブル・フェイス。
■監督と主演女優たち
監督のエラン・リクリス(Eran Riklis)は、ユダヤ系のイスラエル人。
調べてみると『カップ・ファイナル』(1991年) という作品もある。イスラエル人とパレスチナ人のサッカーをめぐる友情と破綻を描いたこの映画は、いつだったか正確に記憶していないが、「イスラエル映画祭」(東京)で見ている。ああ、あの映画の監督か、と。
モサド工作員を演じている女優のネタ・リスキン(Neta Riskin)は、ユダヤ系のイスラエル人。日本での劇場公開作品はないが、イスラエルでは評価されているようだ。
ヒズボラ幹部の元愛人を演じているのは、ハリウッド映画にも出演しているゴルシフテ・ファラハニ(Golshifteh Farahani)というイラン人の女優。『バハールの涙』(2019年)ではISISと戦うクルド人戦士を主演している。
イラン人が、敵対国であるイスラエルの映画に出演するなど考えにくいが、この女優はイラン国内ではいろいろ批判されており、現在はイランから出国したままパリ在住なのだそうだ。
中東をめぐる情勢は、ヨーロッパ情勢ともからんで、なかなか外部の人間には理解がむずかしい。ハッキリと白黒がつけられるほど単純ではないのだ。
<ブログ内関連記事>
■ヨーロッパとムスリム移民
■米国とイスラエル。イランとヒズボラ
■シリア・レバノン・パレスチナの宗教状況
■「イスラーム国」(ISIS)
(2023年11月13日 情報追加)
(2023年11月25日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年12月23日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年6月24日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年11月19日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年10月22日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2020年12月18日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2012年7月3日発売の拙著です 画像をクリック!)
end
















.png)
.png)
.png)
.png)


.png)