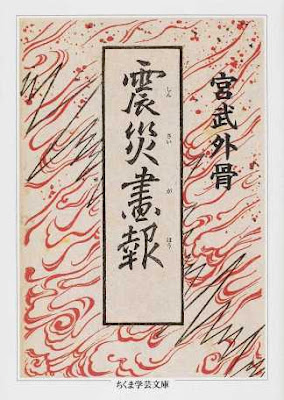■
物流(ロジスティクス)で読むアジアのいま
物流(ロジスティクス)は面白い。
とくに
経済成長著しい「新興国」のモノの動きを下支えするロジスティクス(物流)関係者は縁の下の力持ちといってよい。
物流は正面切ってスポットライトがあてられることがあまりないだけだけに、本書の試みはたいへん歓迎されるものだ。
しかも知られざるアジアの状況である。
アジアで「物流革命」が起きている、まさにその現場からのリポートが面白くないはずがないえはないか。
モノを動かすのはヒトである。東南アジアの物流関係者の熱い息吹を感じることのできるドキュメントである。なにごとであれ、現場が面白い。ディテールが面白い。
本書の「あとがき」に、なぜ物流かについての説明がある。
物流を取り上げたのは、ASEANで長年、進出日系企業を観察していると適地生産、再編は域内だけでなく中国とも絡み、かなりのスピードで進行していることが分かり、日系企業の生存を賭けた戦いは、物流に深くかかわっているからである。
本書は、部品から完成品、生鮮食品から生花まで、分秒を競う21世紀のシルクロードを生産現場からコンテナ車のあとを追ってつぶさに検証した8ケ月の記録だ。
エヌエヌエーは、アジア全域で配信している日本語の日刊情報誌である。
■
インターネット時代だからこそ、さらに物流の重要性は高まっている
インターネット時代はモノは重要性が低くなるなどと日本では一時期考えられたこともあったが、それは大間違い。ネットショップの普及で、かえって小口配送は活発化している。
インターネットは「情報流」と「商流」と「カネ」についてはビジネスを促進するが、
物理的な実体をもつモノは永久に消えてなくなることがない。だから、物流は永久に消えることはないだろう。テレポーテーションはまだまだSFの世界の話である。
現代の日本人の消費生活が、中国やASEAN諸国からのモノの輸入によって大きく成り立っていることは、多くの人が知るようになっている。
現在では「産地表示」が当たり前となったので、スーパーの店頭でインドネシア産のエビやタイ産のイカを目にするのも日常的になっている。チリ産の養殖サーモンすら、なんとタイの日系水産会社で加工されて日本に輸入されているのである!
衣類も家電製品もその多くが、中国やASEAN諸国の日系メーカーの工場から輸入されているのである。
その意味でも、アジアの物流事情がどうなっているのか、アジアビジネスにかかわりがなくても知っておきたいところである。
さらに将来を考えれば、アジアでも今後は小口配送が本格普及するだろう。そうなると、ASEANと日本と中国のあいだの物流は、さらに爆発的に拡大していくことになるはずだ。
■
アジアの道は陸海空
タイトルには「アジアの道」とあるが、
道は「陸路」だけではない。「海路」も「空路」も道である。
最初から「陸路」と河川が中心だったヨーロッパとは発展の仕方が異なるのである。現在でも、各国の国内物流は「陸路」が中心だが、国を超える物流は「海路」が中心である。
アジアで「物流革命」とは、これまで「海路」が中心だった物流が「空路」へ、そしてまたASEAN諸国域内の「陸路」へと広がりつつあることである。
ベトナム戦争が終結し、「インドシナを戦場から市場へと」という提唱が1991年になされてから20年、
「メコン圏」を東西南北で縦貫する「東西回廊」と「南北回廊」の整備が着々と進んでいる。
本書が出版されたのは2008年、取材が行われたのは2007年4月からの8ヶ月間であり、すでに4年前のことである。
この4年間のあいだには陸上交通網の整備がさらに進んだだけでなく、航空便でも全日空が沖縄に物流ハブ基地を開設するなど大きく進展している。
また、2009年のバンコク国際空港の封鎖や、2011年には「3-11」の原発事故による日本産品の輸入禁止など、物流がらみで、さまざまな事件も発生している。
ぜひまた、あらためて「物流最前線」の取材をまとめていただきたいものだと思う。
とりあえずは、この一冊で、ASEAN諸国と中国、日本のあいだのモノの動きについて実感していただきたいと思う次第だ。
日本の企業世界のなかでクチにされる
「三現主義」とは、「現場・現物・現実」のこと。
物流「現場」でモノという「現物」が動く「現実」を、アジアにかかわるビジネスパーソン以外にもディテールごと知ってほしいものである。
モノの動きにかかわるのはヒトなのである。
目 次
はじめに
第1章 空の道
ASEANから飛ぶマグロ【プーケット、バリ、ジャカルタ→日本】
部材空輸、中国向け加速【バンコク国際空港(タイ)】
域内最大ハブ、業界も絶賛【チャンギ空港(シンガポール)】
苦闘する第3のメガ空港【クアラルンプール国際空港(マレーシア)】
シンガポール経由で活路【スカルノ・ハッタ国際空港(インドネシア)】
韓国経由で欧米へ輸出【タンソンニャット国際空港(ベトナム)】
輸出の7割電子部品【ニノイ・アキノ国際空港(フィリピン)】
第2章 海の道
海を走る自動車【タイ、シンガポール、インドネシア】
成長の新港、限界の老舗港【レムチャバン港(タイ)】
コンテナ・石油、世界的ハブ【シンガポール港湾】
5年で貨物量8割増へ躍進【マレーシア港湾】
海賊との終わりなき戦い
日系工場密着で成長続く【インドネシア港湾】
造船などサポート業も成長【ベトナム港湾】
船員養成へ日系船社が力【フィリピン港湾】
第3章 陸の道
片肺の3カ国物流、自由走行へ政治の壁【シンガポール~バンコクを走る(1)】
家電と紙おむつ、相互に国際陸送【シンガポール~バンコクを走る(2)】
アジア回廊のハブ、タイ起点に広がる【シンガポール~バンコクを走る(3)】
南北回廊に押し寄せる中国の熱気【タイ~ラオス~中国を走る(1)】
東西回廊を補完、カジノもある国境【タイ~ラオス~中国を走る(2)】
動き出した東西回廊【バンコク~ラオス~ハノイを走る(1)】
巨大市場へ期待、日系企業【バンコク~ラオス~ハノイを走る(2)】
拠点補完のインドネシア陸路
まず犯罪対策のフィリピン陸路
第4章 21世紀のシルクロード
見えてきた雲南の物流ハブ
広西、中越黄金ロードに
ASEANへターミナル広東
飛躍するインド空運
コンテナ貨物、急増するインド海運
拡大続く中印貿易
あとがき
(2022年12月23日発売の拙著です)
(2022年6月24日発売の拙著です)
(2021年11月19日発売の拙著です)
(2021年10月22日発売の拙著です)
(2020年12月18日発売の拙著です)
(2020年5月28日発売の拙著です)
(2019年4月27日発売の拙著です)
(2017年5月18日発売の拙著です)
(2012年7月3日発売の拙著です)
ケン・マネジメントのウェブサイトは
ご意見・ご感想・ご質問は ken@kensatoken.com にどうぞ。
お手数ですが、クリック&ペーストでお願いします。
禁無断転載!
end

.png)


%E2%97%86.png)