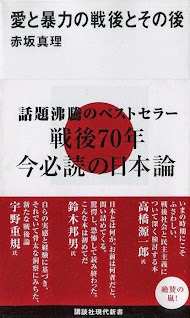2014年5月に出版された『愛と暴力の戦後とその後』は、わたしがジュンク堂の店頭で手に取った2015年4月の時点で、2015年2月の第8刷となっていた。話題のベストセラーになっているようだ。
読むことにしたのは、ベストセラーであることも理由の一つである。この人の評論はすでに
『モテたい理由』(講談社現代新書、2007)を読んでいて面白いと思っていたのだが、あえてまた読むまでもあるまい、と
ベストセラーになってから読むというのはけっして悪いことではない。むしろ、
なぜベストセラーになっているのか自分で検証してみるつもりで読むと、「いま」という時代の日本人が漠然と感じていることをつかむキッカケともなるからだ。
読んでみての感想は、
著者による自問自答を重ねた内容に、「戦後日本」とはいったい何だったのか考えてみるヒントがある、ということだ。おそらく多くの人が同様の感想をもつことだろう。
著者は「まえがき」をこう書いている。短いので全文を引用しておこう。
「これは、研究者ではない一人のごく普通の日本人が、自国の近現代史を知ろうともがいた一つの記録である。
それがあまりにわからなかったし、教えられもしなかったから。
私は歴史に詳しいわけではない。けれど、知る過程で、習ったなけなしの前提さえも、危うく思える体験をたくさんした。
そのときは、習ったことより原典を信じることにした。
少なからぬ「原典」が、英語だったりした。
これは、一つの問いの書である。
問い自体、新しく立てなければいけないのではと、思った一人の普通の日本人の、その過程の記録である。
■
1964年生まれの著者の世代と「戦後」認識
著者は1964年生まれ、わたしとは2歳違いである。ほぼ同世代といっていいだろう。
著者は、個人的な体験をもとに「1980年の断絶」について書いているが、
その年に16歳の著者は1年間アメリカに高校留学していたのだという。日本の高校に不適応だったからだ。アメリカ留学にも挫折して
日本に帰国してから、大きな違和感を抱いたのである、と。
世界的にみれば「1979年」こそ「断絶の年」だ。英国でサッチャー政権誕生、イランでイスラーム革命が勃発、そして年末のソ連によるアフガン侵攻など激動の年であった。
日本にかんしていえば、『ジャパン・アズ・ナンバーワン』というほめ殺し本の日本語訳が出版されたのが1979年だ。その翌年の1980年に「断絶」が顕在化し始めたといえるかもしれない。著者の直感はじつに鋭い。
1980年は松田聖子がデビューした年であった。「革命」と評価を下す同世代人がいる一方、著者にとっては、あまり意味のない出来事だったのかもしれない。だが、
日本にとっても、1980年が断絶の年となったことは確かだろう。
1964年前後生まれの著者の立ち位置は、「戦前」につながる「戦後」の痕跡をところどころに感じることができながら、学校教育やマスコミをつうじて、「戦前」と「戦中」が全面否定されていくなかで育った世代だと要約できるかもしれない。
1962年生まれのわたし個人について言えば、
小学生の頃には地上波では再放送がなかった幻の名作アニメ『アニメンタリー決断』をリアルタイムでテレビで見て学校で話題にしていた世代であり、「戦前」や「戦中」を遠い存在と感じていたわけではない。
だが、その後、学校教育やマスコミをつうじて、だんだんと戦争そのものがタブー視されていったような記憶がある。
追い討ちをかけたのは、政治問題と化した靖国問題ではなかろうか。バブル期のなか、英霊なんてことを口にすることすらはばかれる時代となってしまったのだ。
わたし自身、いまから7年前の2009年8月15日まで靖国神社を参拝することは心理的抵抗があってできなかったのだ。呪縛されていたのである。
だからこそ、
「戦後とその後」を生きてきた日本人が自明と思っていることが、じつは見ないように避けてきた結果に過ぎないことは、著者に指摘されてあらためて、うなづくのである。
以下、本書に関連するトピックについて、個人的な感想をつづってみたいと思う。
■
「愛と暴力」の「敗戦と占領」
『愛と暴力の戦後とその後』というタイトルは、なかなか意味深だ。
2015年は「戦後70年」とされ、日本国内では大きな話題になっているが、じっさいのところ、
「戦後」とよばれる時代区分が、2011年3月11日に東日本大震災と原発事故によって終わっているという認識はすでに広く共有されているのではなかろうか。わたし自身についていえば
、正直いって、あまり「戦後70年」という感慨は湧いてこない。
なぜ「戦後とその後」に生きている日本人は、それ以前の「歴史」から切り離されているように感じるのか? これは本書で提起されている問いを貫いているものだ。
精神的空洞、存在の底が抜けているという感覚、宙ぶらりんの空中浮遊感。なにかが隠されているのではないか?
自分を守るために、臭いものに蓋をして見て見ぬふりをしてきたのではないか?
「臭いものに蓋」という表現は適切ではないかもしれないが、
個人的に大きなトラウマを抱えた人は、それを誰にも語らずに抱え込んでしまうというケースは、日本の戦争体験者だけでなく、
ホロコーーストの体験者にも見られることだ。そんなことはクチにするのはおろか、考えたくもない、と。
おそらく最初は見て見ぬふりをしてきたのだろう。だが、こういう自覚をもっている段階はまだいい。それはその個人、その世代が抱えている個人的、世代的トラウマであるからだ。これは個別に解消するしかない。
だが、
敗戦経験をもった世代の次の世代の人間にとっては、「最初から隠されていたもの」となってしまっていることになる。存在そのものを知らないということになってしまう。そこに問題がある。
■
合理的機制と精神的解離
精神的に抑圧しずぎると、かえってはけ口をもとめた感情が爆発するということは、だれもが経験していることだろう。
アメリカ占領軍による「日本改造」から「愛と暴力の戦後」が始まった結果、日本人は「戦中」と一緒に「戦前」も否定し去ってしまったことが、「歴史」からの切り離され感を生み出してきたことは間違いない。
たしかにアメリカ占領軍は、「戦中」の日本を「戦前」の産物として、すべてを否定した。だが、アメリカ占領軍の占領政策が成功したのは、日本人の多くが「敗北を抱きしめた(ジョン・ダウワー)からだ。占領軍を進駐軍と言い換え(・・侵略を進出と言い換える心理的メカニズムを想起する)、日本人の多くがアメリカの占領政策を支えたことはまぎれもない事実である。
見ないふりをしてきたツケがまわってきている。そのツケは精神的空洞をもたらしているし、いわゆるネトウヨに代表されるように
、「いままで騙されてきた感」という過剰なエネルギーの逆噴射もある。
見ないふりをしてきたが、もはや決壊も近いのなのかもしれない。
いわば歴史を無視してきいたことのツケ、
歴史の復讐であり、歴史の逆襲といえるかもしれない
たとえば、わたしも含めて戦後生まれの日本人が教育されてきたことの一つに、
日本に民主主義はなかった、戦争に負けたことによってアメリカ占領軍から与えられたのだという言説がある。これはじつは正しくない。
明治時代の自由民権運動を意図的に無視した言説だ。
占領政策をスムーズに進めるためのインテリジェンス作戦であったと考えるべきだろう。
ある種の洗脳工作である。
アメリカ占領軍による検閲に基づいた情報操作については、すでに多くの指摘や研究が蓄積されている。そしてその流れに乗っかったのが、左派知識人たちによる「戦前」否定の論調である。圧倒的多数の日本人が受け入れたのは、敗戦を終戦として「抱きしめた」からである。上からの一方的な受け身ではなかった。
最初は主体的な選択の結果であったのだが、その経緯は忘却され
、「受け入れた歴史」をそのまま無意識レベルにまで浸透させ内面化させてしまったのである。その意味では、
戦時中と同様に、「戦後」もまた、意識的な選択によって「集団催眠状態」にあったというべきかもしれない。
「隠れた神は恐ろしい」という表現もある。だがそれは「隠されてきた」わけではない。見ようと思えば見ることはできるし、知ろうと思えば知ることはできる。すでに多くの論者が、アメリカ占領軍が日本と日本人に何をしてきたのかを解明している。
だが、知ろうという気持ちを起こさなければ、最初からなかったことにされてしまっているもの。あえてそこに目を向けさせないように、巧妙に違う方向を見るように仕向けられてきたこと。そのことにまったく気がつかないできたということ。じつに恐ろしいことではないか!
考えてみれば、
著者が指摘するまで、憲法の「憲」が、憲兵の「憲」であることなど考えたこともない。多くの人もまた虚を突かれたのではないか?
正直なところ、わたしももまた
憲法に該当する英語が、constitute(=構成する)という動詞の名詞形である Constitution という以外は考えていなかった。
日本語に食い込んで抜けない漢字の呪縛については、あらためて考える必要があることを痛感する。
言語明瞭意味不明なのは米語由来のカタカナ語だけではなく、戦中の八紘一宇(はっこういちう)などの漢字語もまた同様である。
■
歴史の「断絶」と、それにもかかわらず存在する「連続性」
日本の旧植民地や被占領地の人たちが親日的な発言をしたり、感謝を表現することがある。日本のおかげで独立できたのだとか、植民地時代をなつかしむ発言、とか。
そういう話をきくと、
なんだか面映ゆい思いをしたり、申し訳ない気持ちになったり、あるいは
なぜ感謝されるのか肌感覚でピンとこないということもあろう。
かれらが評価しているのが、日本人自身が否定的に捉えている「戦中」であり「戦前」であるからだ。だから、評価されてもいまひとつピンとこない、あるいはなぜ評価されるのかわからないという気持ちになる。「戦中」や「戦前」は、「戦後」からみて否定されるべき時代ではなかったのか、と。
「戦後」と「その後」を生きてきた日本人にとって、「戦中」と「戦後」とが「断絶」しているのに対し、旧植民地の人たちのなかでは「連続」しているのである。もちろんノスタルジーということもあって、過去が美化される傾向があるのかもしれない。だが、
かれらの発言によって、かれらのなかで生きている日本人観と、じっさいに生きている生身の日本人の意識とのあいだにギャップが存在することを知ることができる。
歴史の断絶と連続性回復というテーマで想起するのは、ドイツ再統一によって消滅した国家である東ドイツ(=ドイツ民主共和国)のことである。ドイツもまた「戦後70年」であるが、この事実に目をつぶるべきではない。
敗戦後の冷戦構造のなか東西分割されたドイツだが、東ドイツはソ連、西ドイツはアメリカとイデオロギーをまったく異にする支配者のもとで異なる国づくりを行い、その結果、ドイツ戦後史にかんしては異なる歴史をつくりあげることになった。
西ドイツは、併合した側なので歴史に断絶はない。だが、
併合された側の東ドイツは、東西再統一がなされて以後の歴史とそれ以前の歴史とに大きな断絶が生まれている。それが、旧東ドイツ国民のあいだで鬱屈した不満を産み出していることが、これまで指摘されてきた。
いまにいたるまで旧東ドイツ出身者が感じている精神的な違和感は、
みずからの「歴史」が否定されたこと、つまりアイデンティティを否定されたことにほかならない。経済的な格差だけが原因ではないのだ。
「再統一」から25年以上たっても、断絶した歴史を連続したものに切り替える心理的作業は完成していないのである。
現実問題としては、「戦前」を否定したのが西ドイツであり、「戦前」がそのまま温存されたのが東ドイツというねじれ構造がある。西ドイツの戦後史は、ある意味では日本の戦後史と似ている。もちろん、安直な比較は無意味である。
「断絶」後の歴史を、どう「断絶」前の歴史と「つなぐ」か、これはドイツなど敗戦国共通の課題だが、ある意味では日本人が抱えている問題と共通するものがあるように思われる。
日本人は「戦後とその後」の現代ドイツ史で、思考実験してみることも必要かもしれない。もちろん、安直な比較論は有害であるが。
■
断絶した「戦後とその後」と「戦中・戦前」を「つなぐ」ために
正常化 ノーマリゼーションのプロセスがいま進行中であると、わたしは考えている。それはけっして右傾化でもなんでもない。「進歩派」であったはずの左派が頑迷な「保守派」となる。
日本の場合、「戦前・戦中」と「戦後」を連続性を担保してきたのは、端的にいって天皇制である。
もちろん、
近代天皇制は明治国家にようる「作られた伝統」であり、それ以前の前近代の天皇制(・・この表現じたいは昭和以前には存在しなかった)とは、制度としては「断絶」がある。だが、
天皇家の血筋によって「連続」が保たれてきたのである。
明治時代以降、
近代化を推進するなかで、国民教化の観点から、西欧社会におけるキリスト教にかわる精神的権威として天皇の神格化が行われたのだが、これはあくまでも世俗の政治権力が設計して構築した「近代の産物」であり、当然のことながら「創られた伝統」である。
「神格化された天皇」像は、大東亜戦争の敗北によって完全に潰えるに至る。
「神話」は否定されたが、同時に「歴史=物語」も一緒に捨て去られてしまった。その後の、
日本人の精神的空洞はこれに起因すると主張する論者は少なくはない。三島由紀夫や小室直樹の問題提起もまた、現在では忘れ去られているのかもしれない。
敗戦によって「神話」は否定されたが、「高度成長」という大きな「物語」が作り出された。「企業戦士」という表現は、ある種の代償行為のような響きをもつ。だが、
「高度成長」の達成後は、日本人が共有するあらたな「物語」が生まれることなく、日本も日本人も迷走を続けている。
思うに、
日本と日本人が「敗戦」による「終戦」という断絶を体験しながらも生き延びてこれたのは、昭和天皇という、戦前と戦後を貫く存在が、生身の肉体を備えた一人の人間によって「断絶」をつなぎとめてきたからだ。これは著者も指摘するとおりだ。
個人的には、昭和63年(1988年)に昭和天皇が崩御したとき(・・その時点ではまだ「昭和天皇」という諡号(おくりな)は決まっていなかった)、これでなにかがすべて終わったという思いに囚われた。ほんとうは、この時点ですでに「戦前・戦中」と「戦後」を連続体とした昭和時代の終わりとともに、「戦後」は終わっていたのかもしれない。
昭和天皇の長男である今上天皇陛下の最大の貢献は、つねに戦没者の慰霊をつうじて「戦中」を喚起させていただいていることだろう。「戦中」と「戦前」そして「戦後とその後」の「連続」を身を以て体現しておられるのである。
度重なる迫害を乗り越え、離散のなかでも生き延びてきたユダヤ民族にとっては、律法と教典が民族性を担保するよりどころとして機能してきた。日本民族にとってそれに該当するのは、「万世一系」の天皇という存在ではないか、と。
以上、『愛と暴力の戦後とその後』 を読んで感じたことを、個人的な感想として書き連ねてみたが、当然のことながら、読者によって感じることはさまざまだろう。
『愛と暴力の戦後とその後』 という本は答えを導き出した本ではない。一人の日本人が、一人ひとりの日本人に向けて
問いを提示した本である。
読者自身が考えるためのキッカケの本として、再読、三読してみる意味のある本であるといえよう。それほど、大きな問いなのである。答えがでることのない・・・。
(画像をクリック!)
目 次
プロローグ 二つの川
第1章 母と沈黙と私
第2章 日本語は誰のものか
第3章 消えた空き地とガキ大将
第4章 安保闘争とは何だったのか
第5章 1980年の断絶
第6章 オウムはなぜ語りにくいか
第7章 この国を覆う閉塞感の正体
第8章 憲法を考える補助線
終 章 誰が犠牲になったのか
エピローグ まったく新しい物語のために
著者プロフィール
赤坂真理(あかさか・まり)
1964年、東京生まれ。慶應義塾大学法学部卒。作家。1990年に別件で行ったバイト面接で、なぜかアート誌の編集長を任され、つとめた。編集長として働いているとき自分にも原稿を発注しようと思い立ち、小説を書いて、95年に「起爆者」でデビュー。著書に『ヴァイブレータ』(講談社文庫)、『ヴォイセズ/ヴァニーユ/太陽の涙』『ミューズ/コーリング』(ともに河出文庫)、『モテたい理由』(講談社現代新書)など。2012年に刊行した『東京プリズン』(河出書房新社)で毎日出版文化賞・司馬遼太郎賞・紫式部文学賞を受賞。神話、秘教的世界、音楽、そして日々を味わうことを、愛している。(カバー袖より)
PS 『東京プリズン』という小説作品について
このブログ記事をかいてから、著者の小説作品である
『東京プリズン』(河出文庫、2014 単行本諸般 2012)を読んだ。
『愛と暴力の戦後とその後』 とあわせて読むと、より著者の表現したかったことが理解できるのではないか、と思う。
この長編小説は私小説ではないが、
著者自身の体験をもとにした小説は、日本と日本人にとっての「戦後」を、より広くかつ深い次元で考えることができるのではないかともう。とく
に16歳の著者が体験したアメリカという異世界についての描写は、じつによく言語表現されていると感じた。
1980年という舞台設定は、1980年代後半のバブル期に激化した「日米経済戦争」以前であり、しかも崩御によって昭和天皇という諡号(おくりな)が命名される以前の時代である。「日米戦争」と「東京裁判」、そして天皇の責任問題などについて考えるには、タイミングとしても悪くない。
ネイティブアメリカン(先住民)、日本人、ベトナム人… 共通するのは、戦争において殺戮された人たちであるということだ。殺されたのは軍人だけではない。空爆や原爆投下で多数の一般市民が殺されたのである。
「東京裁判」を高校の授業の一環としてディベート形式で行うという設定から、いかなる議論が飛び出してくるのか?
『愛と暴力の戦後とその後』は、小説という形式では書かなかったエッセイといえるかもしれない。
(2015年8月23日 記す)
<関連サイト>
下記サイトで 『愛と暴力の戦後とその後』の第1章が読める
日本にとってアメリカとは何か-戦後日本が抱えた無意識の屈折-【特別公開】赤坂真理『愛と暴力の戦後とその後』1 (現代ビジネス、2015年8月13日)
なぜ原爆投下による民間人大虐殺は罪に問われないのか?-日本人に埋め込まれた「2つの思考停止」-【特別公開】赤坂真理『愛と暴力の戦後とその後』2 (現代ビジネス、2015年8月14日)
なぜ日本人は昭和天皇を裁けなかったのか-【特別公開】 赤坂真理『愛と暴力の戦後とその後』3 (現代ビジネス、2015年8月15日)
<ブログ内関連記事>
■
「戦前・戦中」と「戦後」を連続性のものとして捉える
『王道楽土の戦争』(吉田司、NHKブックス、2005)二部作で、「戦前・戦中」と「戦後」を連続したものと捉える
・・この本に収録された安倍晋三と石破茂という、1950年代中期生まれの「ポスト団塊世代」の二人の自民党政治家・・(中略)・・ 「1954年生まれの安倍晋三、1957年生まれの石破茂という「ポスト団塊世代」の政治家二人。奇しくも復活した第二次安倍内閣で総理大臣と自民党幹事長(2014年当時)という要職についている二人である。
安倍晋三は満洲国で統制経済を主導した「革新官僚」岸信介の孫である。
石破茂は大陸や半島に海を挟んで最前線のある島根出身の政治家である。著者は、
団塊世代と団塊ジュニアにはさまれた「ポスト団塊世代」に、「戦前・戦中」と「戦後」をつなぐものがあるとみているのだろうか?
「戦前・戦中」と「戦後」はいっけん断絶したようにみえて、じつは根底のところでつながっているのである」
書評 『マンガ 最終戦争論-石原莞爾と宮沢賢治-』 (江川達也、PHPコミックス、2012)-元数学教師のマンガ家が描く二人の日蓮主義者の東北人を主人公にした日本近代史
書評 『戦争・天皇・国家-近代化150年を問い直す-』(猪瀬直樹・田原総一郎、角川新書、2015)-「日米関係150年」の歴史で考えなければ日本という国を理解することはできない
「神やぶれたまふ」-日米戦争の本質は「宗教戦争」でもあったとする敗戦後の折口信夫の深い反省を考えてみる
書評 『「昭和天皇実録」の謎を解く』(半藤一利・保阪正康・御厨貴・磯田道史、文春新書、2015)-「正史」として歴史的に確定した「知られざる昭和天皇像」
・・福澤諭吉の有名なフレーズ「一身にして二生を経る」をまさに体験された昭和天皇
書評 『沖縄戦いまだ終わらず』(佐野眞一、集英社文庫、2015)-「沖縄戦終結」から70年。だが、沖縄にとって「戦後70年」といえるのか?
■
日米戦争と、敗戦による「国家改造」後の日本
「神やぶれたまふ」-日米戦争の本質は「宗教戦争」でもあったとする敗戦後の折口信夫の深い反省を考えてみる
・・アメリカは「十字軍」、日本は「聖戦」という表現をつかっていた日米戦争
『日本がアメリカを赦す日』(岸田秀、文春文庫、2004)-「原爆についての謝罪」があれば、お互いに誤解に充ち満ちたねじれた日米関係のとげの多くは解消するか?
書評 『東條英機 処刑の日-アメリカが天皇明仁に刻んだ「死の暗号」-』(猪瀬直樹、文春文庫、2011 単行本初版 2009)
書評 『ワシントン・ハイツ-GHQが東京に刻んだ戦後-』(秋尾沙戸子、新潮文庫、2011 単行本初版 2009)-「占領下日本」(=オキュパイド・ジャパン)の東京に「戦後日本」の原点をさぐる
書評 『原発と権力-戦後から辿る支配者の系譜-』(山岡淳一郎、ちくま新書、2011)-「敗戦国日本」の政治経済史が手に取るように見えてくる
・・米国支配下の日本という枠組みで理解できるのが原子力政策だ
日米関係がいまでは考えられないほど熱い愛憎関係にあった頃・・・(続編)-『マンガ 日本経済入門』の英語版 JAPAN INC.が米国でも出版されていた
書評 『国際メディア情報戦』(高木 徹、講談社現代新書、2014)-「現代の総力戦」は「情報発信力」で自らの倫理的優位性を世界に納得させることにある
・・国際世論を作り出すのは米英系のメディアであることを肝に銘ずるべし。それが現実だ
■
日本国憲法
書評 『憲法改正のオモテとウラ』(舛添要一、講談社現代新書、2014)-「立憲主義」の立場から復古主義者たちによる「第二次自民党憲法案」を斬る
書評 『自民党憲法改正草案にダメ出し食らわす!』(小林節+伊藤真、合同出版、2013)-「主権在民」という理念を無視した自民党憲法草案に断固NOを!
■
旧植民地の人たちにとっての日本
映画 『KANO 1931海の向こうの甲子園』(台湾、2014年)を見てきた-台湾人による台湾人のためのスポ根もの青春映画は日本人も感動させる
・・いくら「戦後」の日本人が否定しようが、「戦前」の日本人が残した遺産は否定し切れまい。そして「戦前」の日本が台湾人のアイデンティを形成していることを、日本人は直視しなければならない
■
1960年代生まれの「二人のマリ」
書評 『国境のない生き方-私をつくった本と旅-』(ヤマザキマリ、小学館新書、2015)-「よく本を読み、よく旅をすること」で「知識」は「教養」となる
・・
マンガ家のヤマザキマリ氏は1967年生まれ、小説家の赤坂真理氏は1964年生まれ。この二人の「マリ」は、わたしより若干若い人たちだが、共通する経験と時代感覚をもちながらも、
日本の現実への「違和感」の質的な違いが感じられて面白い。
ヤマザキマリ氏は14歳で、赤坂真理氏は16歳で、それそれイタリアとアメリカに出国した経験をもっていて、その経験のもつ意味を言語化しようとした内容である点が、とりわけ興味深い。
(2015年8月23日、2016年8月23日 情報追加)
(2023年11月25日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年12月23日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年6月24日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年11月19日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年10月22日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2020年12月18日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2020年5月28日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2019年4月27日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2017年5月19日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2012年7月3日発売の拙著です 画像をクリック!)
ケン・マネジメントのウェブサイトは
ご意見・ご感想・ご質問は ken@kensatoken.com にどうぞ。
お手数ですが、クリック&ペーストでお願いします。
禁無断転載!
end