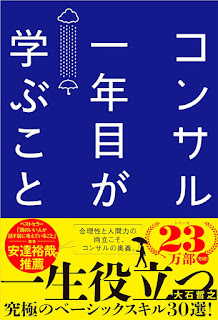SNSの X(旧twitter)では大々的に取り上げられているのが、インバウンドで大量に押し寄せる中国人たちである。そのあまりにも非文明的で迷惑きわわりない振る舞いに激しい怒りを感じている人も少なくないだろう。
その一方、あまり取り上げられていないのが、中国から流入がつづく「新移民」である。
「新移民」は、2000年代以降の現象である。習近平体制になってから社会の閉塞感がつよまるなか、ビザ要件が緩和された日本に移住してくる中国人たちのことだ。1990年代に移住してきた「新華僑」とは異なるカテゴリーに属する人たちだ。
資産規模からいえば、アリババの創業経営者ジャック・マーに代表される、スーパーリッチな創業経営者たちだけではない。不動産バブルの恩恵にあずかり、資産を売却して日本に不動産を購入する都市住民の中間層たちもまたそうだ。だがかれらだけではない。政治的な自由を求めるリベラル派知識人たちもまたそうだ。
いずれも習近平による「ゼロ・コロナ政策」がもたらした経済社会の閉塞感に嫌気がさしているだけでなく、中国の将来に希望がもてない状況にある。大学が狭き門で、かつ就職機会も限られているため、大学をでても職がない若者たち。
中国から流入がつづく「新移民」にかんしては、その是非にはさておき、実態についてはあまり知られていない。わたしにも個人的な知り合いがいるが、あくまでも大河の一滴というべきで、その全体像をつかんでいるわけではない。
昨年9月に出版された『日本のなかの日本』(中島恵、日経プレミアシリーズ、2024)と、ついい先日出版されたばかりの『潤日(ルン リィー) 日本へ大量脱出する中国人富裕層を追う』(舛友雄大、東洋経済新報社、2025)を読むと、「新移民」の実態がおぼろげながら見えてくる。
「潤」(ルン)とは、最近はやりの中国語で、中国を脱出する中国人のことを指している。英語の Run と音がおなじなので、そういう意味が生まれたのだという。
「潤日」(ルン リィー)として日本に流入していくる「新移民」が増大した結果、すでに日本人も日本語もまったく介在しない中国人だけの生活空間が、リアルだけでなくネットでも成立しているのである。その空間のなかでなにが進行しているのか、外部からは窺いようがない。欧州で拡大中のイスラーム・コミュニティのような状態か。
労働力不足という理由で、経団連など経済団体の後押しを背景にした政治的思惑で中国人の流入が増加しているわけだが、先住者である日本人との軋轢も増大していることは、否定できない事実である。それだけでなく、もともと中国人内部にあったさまざまな対立関係だけでなく、「新移民」と「新華僑」のあいだの軋轢もあるというからややこしい。
さらに今後は、「新移民」の二世たちがビジネスエリートとして、あるいは官僚エリート、そして政治エリートとして、日本の政治経済に大きな影響をあたえるであろうことも、けっして絵空事とは言えない状況になりつつある。
東南アジアのタイのようになってしまう可能性もないとはいえない。タイ王国では、日本側ビジネスのカウンターパートになりうるのは、ほぼすべてが華人系エリートである。これは、タイで仕事をしていたことのあるわたしの実感である。
「アングロ・チャイニーズ」というべきかれらは、居住国の言語だけでなく英語で思考することもできるエリート層だ。東南アジアで例外的なのは、中国人に対してあまり融和的ではないベトナムくらいだろうか。スハルト政権崩壊後に大規模な反華僑暴動が発生したインドネシアでは、華人エリートは政商という形で政治家に接近する。
タイのように実質的な華人支配状況がいいか悪いか、その是非は別にしても、そのような状態になってしまうことを回避したいのであれば、量的な「移民制限」は絶対に必要である。人口構成の点からいって、先住民との比率が逆転するような事態が発生すると、なにが起こるかは火を見るより明らかだ。
「帰化」して日本国籍を取得する場合には、巨額な投資など含めた日本社会への「貢献」を求めるのが当然であるだけでなく、日本国家と日本国旗への「忠誠」を求めることも絶対に必要になる。
わたしがそう考えるのは、それが諸外国では当たり前のことだからだ。米国では帰化して米国の市民権を獲得する際には「星条旗への忠誠」が求められる。このセレモニーは全米各地で毎週行われている。
これまた、タイ王国の事例だが、国内で反共活動を続けていた国民党軍の残党が最終的に帰順したのち、かれらを死傷率のもっとも高い最前線に送り込んでいる。国家への忠誠心を「見える化」する方法の最たるものであろう。
忠誠度に問題が発覚したら、「帰化」の認可の取り消しも行うべきだ。主権国家の国民になるということの意味はきわめて重いのだ。だからこそ、帰化して日本の「新国民」となった人間は、つねに見られていることを意識して生きなくてはならないのである。
もちろん「移民」に対する見解は、その本人にとっても、受け入れる側にとっても、個々人によってさまざまであろう。とはいえ、なによりもまず実態を知り、変化しつつる状況を注視していく必要がある。なにごとも功罪両面があることを認識しておかなくてはならない。
そのためには、事実を知ったうえで議論することが必要である。国籍(=ナショナリティ)と民族性(=エスニシティ)の乖離は、古くて新しい問題なのだ。
目 次プロローグ 日本にいるのに、日本語が下手になる私第1章 日本人が知らない、中国人 SNS の世界第2章 中国人だけで回す経済ネットワーク第3章 持ち込まれた中国的論理第4章 日本に来たい中国人 中国に帰りたい中国人第5章 多層化していく社会エピローグ 日本で暮らし働いた黄さんのささやかな夢
目 次プロローグ第1章 世界の現象としての潤 run第2章 タワマンに住む人々第3章 新お受験戦争第4章 引退組企業家安住の地第5章 独自のエコシステム第6章 地方という開拓地(フロンティア)第7章 焦燥する中間層第8章 リベラル派知識人大集結第9章 抗議者、小粉紅、支黒、大外宣エピローグ
<関連記事>
【日本に押し寄せる中国人の富裕層・知識人】急増する在日中国人の社会階層/キーワードは「資産・教育・自由」/東京の“香港化”/日中を行き来する中国人/日本の受け入れ態勢/東京と関西の違い(ゲスト:早稲田大学教授・岡本隆司氏、ジャーナリストの舛友雄大氏)
【日本は「潤日」に備えよ】ジャーナリスト舛友雄大/潜在的には800万人/札束で1億円の送金も「地下銀行」の実態/“まるでバブルの日本”会員制クラブに潜入取材/今は第3次訪日ブーム【1on1】(ゲスト:『潤日(ルンリィー)』の著者、舛友雄大氏)
(2025年3月10日 項目新設)
(2025年4月24日、10月19日 情報追加)
<ブログ内関連記事>
(2023年11月25日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年12月23日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年6月24日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年11月19日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年10月22日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2020年12月18日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2012年7月3日発売の拙著です 画像をクリック!)
end