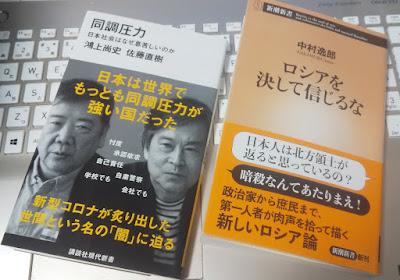「福田村事件」とは、千葉県東葛飾郡福田村(現在の野田市)でいまから100年前の1923年9月6日に起こった事件のことだ。
福田村は鬼怒川が利根川に合流するあたりで、利根川左岸に位置している。千葉県と茨城県の県境に近い。
震災後の流言飛語から生まれた自警団が暴走し、不安心理と興奮状態にある集団内で発生した同調圧力が集団狂気に変わり、日本人の集団が有無を言わさず虐殺された事件である。
関東大震災(1923年9月1日)は、大規模自然災害にとどまらない。官憲が無責任にも公表した虚偽情報が核となり、それが流言飛語となってあっという間にクチコミで民間に拡散したことで悲劇が生まれたのである。
悲劇の中心はいうまでもなく「朝鮮人虐殺」である。だが、虐殺されたのは朝鮮人だけではない。中国人もそうであり、また大杉栄など日本人の無政府主義者も含まれていた。
忘れてはならないのは、というよりも忘れられてきたのは、いやそれもまた正確ではない、意図的に隠蔽されてきたのは、それ以外の日本人も虐殺の被害にあっていたという知られざる事実だ。そのひとつが「福田村事件」である。
先にもみたように、香川県の被差別部落からきた薬売りの行商人グループが朝鮮人と誤認され虐殺された事件である。殺気だった自警団によって、15人のうち10人が無残にも殺害され、死体は利根川に投棄されたという。
恐るべき事件である。おぞましい事件である。無実の人たちが、有無を言わさず惨殺され、しかも死体が遺棄されたのである。遺骨収集もかなわなかったのである。
恐るべき事件であったことは、被害者たちにとっては言うまでもない。だが、加害者の側にとっても、その後は思い出したくもない、考えたくもない事件であったのだ。
だからこそ、長年にわたって語られることもなく、当事者の世代が消えたあともなお、知られることもなかった事件なのである。
■『福田村事件 ー 関東大震災・知られざる悲劇』は読み継がれるべき本
本書『福田村事件 ー 関東大震災・知られざる悲劇』は、昨年から千葉県内のリアル書店では平積みにされていたが、関心外のこととして無視してきた。
だが、これはそういうことではいけないと気づいたのは、たまたまWikipediaなどで関連情報を読み込んで驚愕の事実を知った昨日のことだ。さっそくリアル書店で購入して通読したのである。
関東大震災100年を前にした昨年2023年7月の初版だが、わたしが購入した時点ですでに5刷(2023年10月)となっている。かなり読まれているようだ。amazonのレビューも多数にぼっている。(*なお、第3刷で本文の一部が書き直されたようだ)。
事実を事実として語らせるという抑えた筆致が、かえって事件の恐ろしさを浮かび上がらせる。 そんな本である。
流言飛語の核となったのは官憲による虚偽情報である。フェイク情報である。これがあっという間に流言飛語として口伝えに拡散し、個々人が抱える不安心理が集団のなかで増幅し、同調圧力が常軌を逸した集団狂気となって虐殺を引き起こしたのである。恐るべきメカニズムである。
まさにSNSで現に起こっている事態であり、独りよがりな「正義感」にもとづく批判中傷の発言がネット上の集団リンチ状態を引き起こし、バッシングの対象となった被害者が精神的に追い込まれて自殺するなどの悲劇が後を絶たない。
だが、はたして21世紀の現在、このメカニズムはネット上だけにとどまらないのではないか?
事件の舞台となったのは100年前の日本の一農村だが、つい3年前の2021年にはトランプ主義者たちによる「米国議会議事堂襲撃事件」などが起きていることを考えれば、けっして過ぎ去った過去の話だとは思えない。この事件では死者もでている。いつどこで起こっても不思議ではないのだ。
(映画『福田村事件』予告編)
■「福田村事件」を知るためには「朝鮮人虐殺」についてしらなくてはならない
本書『福田村事件』は、「福田村事件」だけを取り上げたものではない。
この事件を考えるための前提としての「朝鮮人虐殺」について、千葉県流山市在住の著者はとくに千葉県北西部の状況について取り上げている。もともと本書は、千葉県の地方出版社である崙書房から2013年に初版が出版されている。崙書房は廃業していまはない。
「朝鮮人虐殺」が集中的に発生したのが東京の下町に該当する地域だが、首都圏全体で虐殺が行われていた。本書では、江戸川をはさんで対岸にある千葉県北西部の事例が重点的に取り上げられている。利根運河の改修工事や、北総鉄道(現在の東武野田線)の建設現場に朝鮮人労働者が多数働いていたことも本書ではじめて知った。
「朝鮮人虐殺」という事実そのものは知っていても、その詳細までは知らなかっただけでなく、ふだん身近に接してきた土地でそんな蛮行が行われていたことを、いまのいままでまったく聞いたこともなかったこと、文字で読んだことすらなかったことに、おおきな衝撃を受けている。無知を恥じるばかりである。
「福田村事件」は長年にわたって「隠蔽」されてきた。著者自身もまったく知らなかった事件だという。ぜひ活字にしてほしいと頼まれて調査を行い、この事件を掘り起こして書籍化までもっていったのが、10年前にでた『福田村事件』の初版である。
関係者の証言を取ろうにも、ことごとく拒否されたり、取材そのものがたいへん困難なものだったようだ。その事実じたいが、この事件について考える材料になる。そのため、著者は当時の新聞記事を丹念に調べ、すでにおこなわれているさまざまな調査を重ね合わせて、慎重に事実の検証を行っている。
事件からまだ100年しかたっていないのである。100年もたっているのではない。100年しかたっていないのである。100年は3世代でしかないのである。加害者たちとその子孫たちも内心で思うこともあるのだろう。だから、事実を見つめてことばにすることを心理的に拒否する理由はわからなくもない。
被害者を追悼し、被害者のプライバシーを守るのは当然だ。それとは意味が違うが、加害者たちやその子孫たちを非難したところで意味はない。恩讐の彼方で、ノーサイドの立ち位置から、虐殺が行われたという「事実」そのものをしっかりと見つめることが重要なのだ。
事件から 100年たった現在、いま生きているわれわれにとって重要なことは、この事件について知り「教訓」を今後に活かしていくことである。 まずはこの「黒歴史」を知ることがなによりも大事なことだ。
それは戒厳令下で治安出動を行い、朝鮮人虐殺を先導した帝国陸軍の習志野騎兵隊もまた例外ではない。日露戦争における栄光だけが、その歴史ではない。 光と影の両面を見なくてはならないのだ。
習志野騎兵隊の治安出動については、吉村昭氏の『関東大震災』でも取り上げられていたので知っているが、治安出動に参加を命じられた騎兵の立場から書かれた、プロレタリア作家・越中谷利一(1901~1970)による「戒厳令と兵卒」(1928年)のことは、本書ではじめて知った。亀戸駅付近の状況が、検閲による「×」の伏せ字だらけのまま本書に引用されている。(・・ただし、復元された文章も併記されている)。
「シベリア出兵」の出征体験をもつプロレタリア作家・黒島伝治(1898~1943)は、兵士の視点からみた「渦巻ける烏の群れ」などのシベリア戦記が岩波文庫に収録されているので比較的知られている。
シベリア出兵(1918~1925)は、ちょうど関東大震災をはさんだ同時期にあたる。越中谷利一のことはまったく知らなかった。埋もれているのはまったくもって残念なことだ。ぜひ岩波文庫などで復刻してほしいものだ。
関東大震災もそうだが、大正時代は日本近現代史における曲がり角であった。世界大戦時の好景気が泡と消え、格差が深刻化していった時代だった。
とはいえ、「福田村事件」について考える際に重要なことは、けっして日本社会特有の事象と捉えるだけにとどまってはいけないことだ。集団となったときの人間心理と人間行動について、厳しく見つめることが必要である。
同調圧力が生じやすい集団のなかで、いかに個としての正気を保つか。冷静さを維持できるか。きわめて困難な課題であるが、避けてとおるわけにはいかないのである。 つねに意識しなくてはいけないのである。
(画像をクリック!)
目 次はじめに ー 増補改訂版刊行にあたって第1章 マグニチュード7.9の大地震第2章 天災につけこんだ人災第3章 福田村の惨劇第4章 追悼に向けておわりに ー 旧版出版から映画化まで特別寄稿 『A』『A2』から『福田村事件』へ(森達也)福田村事件関連資料主な参考文献
著者プロフィール辻野 弥生(つじの・やよい)1941年、福岡県生まれ。香蘭女子短期大学卒業。流山市立博物館友の会会員。福田村事件の論考を発表。北野道彦賞受賞。
<関連記事>
◆著者インタビュー記事
◆関連記事
・・「大震災による混乱の中、流言飛語により県内でも八千代市や船橋市、習志野市、市川市など各地で住民や自警団、軍人が朝鮮人を殺傷。合わせて三百数十人が殺害されたといわれる。」
・・「大震災から101年目となった1日、船橋市営馬込霊園であった追悼式。実行委員会が主催し、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)県西部支部常任委員会が主管した。霊園内の一角には、一枚岩の「関東大震災犠牲同胞慰霊碑」(台座を含め高さ約4メートル)などが建立されている。
当時は船橋市から北の鎌ケ谷市にかけて鉄道敷設工事が行われ、多くの朝鮮人労働者が働いていた。大震災発生後、朝鮮人にまつわるデマが飛び交い、船橋、市川市などで自警団や住民らによる虐殺が相次いで発生。
同支部の資料によると、遺体は船橋市内の墓地に埋めたとされ、慰霊碑が建てられたものの、墓と慰霊碑を現在地に移すことになった63年、碑近くを掘り起こしても遺骨はなかった。行方を探すうちに火葬場近くの田んぼに埋められたことが分かり、掘り出した遺骨は約100体に達したという。
遺骨は現在の慰霊碑区画内に埋葬した。碑の裏面には、虐殺の経緯とともに「犠牲同胞の怨恨(えんこん)は実に千秋不滅」などと刻まれている。」
・・「市川さんは「100年の節目の昨年、映画の公開もあり多くの人が関心を持った」と振り返る。 一方、事件の周知は進んだが、真相を知る「認知」までは途上と課題も指摘する。 昨年公開された事件と同名タイトルの劇映画「福田村事件」について、市川さんは企画段階で製作側に協力した。しかし完成した内容は「行商の人などの描き方がひどい」と憤慨する。 具体的には、行商人らしくない服装や、効果のない薬を売りつける場面、自ら被差別部落出身であることを語る場面などが史実と異なるという。 行商団は香川県が交付した証明書を所持して薬を販売していたほか、当時は現在よりも被差別部落への差別が厳しかったと指摘。 「犠牲者、被害者の名誉を傷つけ、差別が広まってしまう描き方だ」
・・船橋での死者が多いのは、当時は北総鉄道(現在の東武野田線)の建設が行われていたために作業員として働いていた朝鮮人がいたこと、海軍の無線基地があったこと、流言飛語の拡散で拘束された朝鮮人が騎兵隊のある習志野基地に集められ、一部は営倉内で虐殺されたが、その他多数は民間に引き渡されたことがあるようだ
・・9月7日には緊急勅令「治安維持の為にする罰則に関する件」(勅令403号)が出された
(2024年9月14日 情報追加)
(画像をクリック!)
<ブログ内関連記事>
・・「本書の最大の山場は、関東大震災(1923年9月1日)であろう。 著者の山川菊栄にとっても、戦前日本の社会主義運動にとっても、大きな分水嶺となった出来事だからだ。 きわめて個人的な回想が語られるが、流言飛語が飛び交うなか、「朝鮮人」だけでなく「主義者(=社会主義者)」も虐殺の対象になったことが、手に取るようにナマナマしく描写されている。大杉栄夫妻とその子どもが虐殺されたが、山川夫妻と子どもは危うく難を逃れることができたのであった。」
・・関東大震災の際の甘粕憲兵大尉による大杉栄一家虐殺事件も
・・吉村昭氏の『関東大震災』についても言及。同書には戒厳令下に帝国陸軍の習志野騎兵隊が緊急に治安出動したことも記されている
・・プレートには関東大震災に際して虚偽情報を放送したという「黒歴史」にかんする記述はいっさいない
(2023年11月25日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年12月23日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年6月24日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年11月19日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年10月22日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2020年12月18日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2012年7月3日発売の拙著です 画像をクリック!)
end