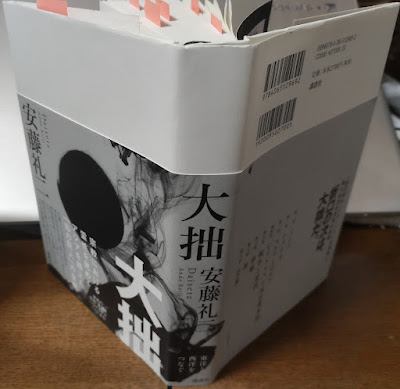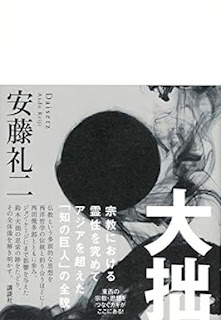『大拙』(安藤礼二、講談社、2018)をようやく読了。大拙とはいうまでもなく鈴木大拙のことだ。購入から5年たってしまった。
安藤礼二氏といえば、大著『折口信夫』を完成させた文芸評論家だが、なぜ鈴木大拙かというと、それは折口信夫の出発点にいわゆる「新仏教」運動なるものがあったことを知ったからだという。
本書『大拙』は、その10年以上にわたる取り組みの成果である。『折口信夫』の副産物というよりも、これだけで「ひとつの世界」になっていると考えていい。
近代化を西洋化として急速に進めていた日本。あらたに流入してきたキリスト教と近代科学に、仏教はどう応えていくのか。この課題に正面から取り組んだのが「新仏教」であり、若き日の鈴木大拙の思索の出発点であった。
鈴木大拙がなぜアメリカに渡り、そこで11年間も過ごしたのか?
生涯にわたる親友であった西田幾多郎とのあいだの相互の影響関係、国際結婚したビアトリスとの関係。初期にはスウェーデンボルグ、後期にはマイスター・エックハルトという西洋神秘主義からの影響などなど。
こういったテーマを深掘りすることで見えてくるものがある。
■「二元論」の克服こそ鈴木大拙の生涯のテーマ
東洋と西洋、仏教とキリスト教、禅と浄土、日本語と英語、ローカルとグローバル・・・
こういったさまざまな二項対立的な二元論的要素を、「二即一」であり「一即二」として、あるいは「多即一」であり「一即多」であるとして、「一元論的」的に把握する思考のあり方こそ、「近代人」であった鈴木大拙が咀嚼し直して世界に向けて展開した禅の思想と実践であり、また同時に盟友の西田幾多郎の哲学であった。
安藤礼二氏の『大拙』は濃厚な内容であり、多岐なテーマにわたっているので読むのに時間がかかるが、すでに没後50年を超えた鈴木大拙はけっして過ぎ去った過去のものではなく、現代の問題をはるかに先取りして思索し続けた存在であることが、読んでいると再確認される。
21世紀の現在の課題は、日本語世界の鈴木大拙と英語世界の D.T. Suzuki とのズレを認識することだろう。
この両者は「一にして二」であり「二にして一」の存在である。とはいえ、日本人は英語世界の D.T. Suzuki をまだまだ知らないのではないか?
(最初から英文で書かれた『禅と日本文化』の原本 筆者蔵書)
日本の敗戦後、80歳を過ぎてから(!)、ふたたび渡米し精力的に活動した鈴木大拙の尽力により、戦後のアメリカで熱狂的に受け入れられ、すでに完全に定着している「ZEN」。むかしからある日本の禅寺の座禅の「禅」。
両者は本質的におなじであっても、その受け取られかた、そのあり方には違いがある。
世界はすでに一体化しているが、一体化しているからこそ、その多様であることに意味がある。人類としての本質的な共通性と、文化による多様性。「一にして多」であり「多にして一」なのである。この認識がきわめて重要だ。
鈴木大拙について考えることは、現代日本人にとっても大いに意味あることなのだ。国際化や国際人とはなにか、その本当の意味を考えるためにも、参照系として想起すべき存在なのである。
(画像をクリック!)
目 次はじめに第1章 インド第2章 アメリカ第3章 スエデンボルグ第4章 ビアトリスと西田幾多郎第5章 戦争と霊性第6章 華厳第7章 禅第8章 芸術後記
著者プロフィール安藤礼二(あんどう・れいじ)1967年、東京都生まれ。文芸評論家、多摩美術大学美術学部教授。東京大学客員教授。早稲田大学第一文学部卒業。大学時代は考古学を専攻し、出版社の編集者を経て、2002年「神々の闘争―折口信夫論」で群像新人文学賞評論部門優秀作を受賞、批評家としての活動をはじめる。2006年、『神々の闘争折口信夫論』(講談社)で芸術選奨文部科学大臣新人賞を受賞。2009年、『光の曼陀羅日本文学論』(同)で第江健三郎賞と伊藤整文学賞を受賞。2015年、『折口信夫』でサントリー学芸賞と角川財団学芸賞を受賞。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたもの)
<ブログ内関連記事>
・・ドラッカーは禅画や水墨画を日本の「表現主義」(Expressionism)とみなしていた
(2023年11月25日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年12月23日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年6月24日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年11月19日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年10月22日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2020年12月18日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2012年7月3日発売の拙著です 画像をクリック!)
end