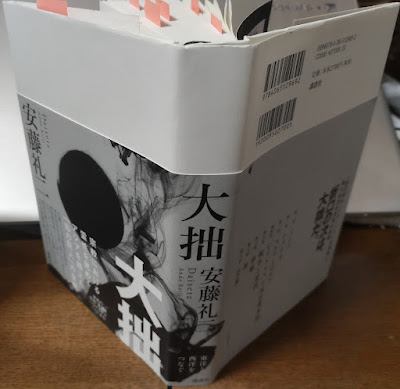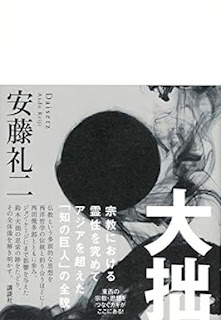■
「ガラパゴス」のどこが悪い?! -日本はそもそも、「本家ガラパゴス」をはるかにしのぐ「超ガラパゴス」なんだけどね(笑)
「ガラパゴス化」という表現を初めて知ったのは、
『ガラパゴス化する日本の製造業-産業構造を破壊するアジア企業の脅威-』(宮崎智彦、東洋経済新報社、2008)のことであった。この本を手にする前に、経済雑誌で見たのかもしれない。
その当時まさに東南アジアはタイ王国のバンコクで、製造業相手の機械部品販売ビジネスに従事していた私から見ても、製造業についてはまったくそのとおりだなと強く納得したのを覚えている。
「ガラパゴス化」とは、太平洋の孤島ガラパゴス島になぞらえた表現。その心は、世界の大勢から孤立した島のなかで、イグアナなど生物が独自の進化を遂げたガラパゴス島の状態を、同様に世界から孤立した島のなかで独自発展を遂げた日本の現状、とくに世界標準から大きく離れて進化している携帯電話について指摘したものだ。
タイをはじめとする東南アジアでは、通信規格が欧州標準の GSM であり、しかも私が従事していた商売は、機械部品の規格品(標準品)を在庫販売する形態のビジネスであったので、余計に同感したのかもしれない。規格品はモジュール化のための基本である。
『ガラパゴス化する日本の製造業』出版後、
「ガラパゴス化」というタイトルの悲観論が世に一気に拡がったのは、「リーマンショック」と「トヨタショック」によって日本の製造業にとっての「円安バブル」というフォローの風が、一気にアゲンストの風に変わったという状況があったためだろう。
ただし、ここでいう「トヨタショック」とは、米国での品質問題がらみのリコール騒ぎのことではなく、その前に顕在化した大幅な販売数量落ち込みのことを指す。
■
『ガラパゴス化する日本』(吉川尚宏、講談社現代新書、2010)をレビューする
本書は、その『ガラパゴス化する日本の製造業』から始まったキーワード「ガラパゴス化」を日本全体に拡大して論じた本である。いっけん難しそうな内容に思えたが、中身は一気に読み進めることができる。
基本的に、経済学者・野口悠紀夫などの所説を踏まえた、日本がおかれている状況にかんする著者の現状分析は正しい。
日本の経常収支構造はもともと内需中心であって、外貨を稼いでいるという日本国民一般の固定観念とは大きく異なり、むしろ巨大な国内市場を抱える米国に近い構造である。
しかし、
日本が人口減少によって縮小している「縮小するガラパゴス」であるのに対して、米国は移民を含めた人口増加傾向にある「膨張するガラパゴス」であるとする点、ここまでは著者の分析には賛成だ。
また
日本の製造業がモジュラー型への移行が必用だという所論にも賛成だ。そのための形式知の重要性についても同感だ。
だが、処方箋にかんしては納得しがたいものを感じるのは、
基本線が悲観論の様相を帯びており、おそらく本人は無意識であろうが、
大企業クライアントのみを相手にしてきたエリートによるエリートのための、上から目線に終始しているからのように思われる。
本書で説く内容の問題は、国全体のマクロレベルの話と、企業や個人といったミクロレベルの主体的な行動とは次元が異なるという点にあることに十分に留意していないことにある。
第2章のおわりで、日本企業と日本国と日本人がとるべき選択にかんするシナリオが8つ提示されている。
◆シナリオの説明(参考)
「① 総ガラパゴス化シナリオ」
「② 若者日本脱出シナリオ」
「③ 霞ヶ関商社化シナリオ」
「④ 国が先導し、若者が中心となる脱ガラパゴス化シナリオ」
「⑤ JUDOシナリオ」
「⑥ 優良企業・優良人材脱出シナリオ」
「⑦ 官民グローバル化シナリオ」
「⑧ 出島シナリオ」
著者が第4章で詳細に論じている 「③霞ヶ関商社化シナリオ」と、その対極にある
「特区」活用型「⑧出島シナリオ」、著者の主張は、この「⑧ 出島シナリオ」にあるようだ。これは別に否定はしない。
ただ、ここでは詳しく説明しないが、私は
個人的には、「⑤JUDOシナリオ」が可能性としては一番高く、「⑥優良企業・優良人材脱出シナリオ」がそれに次ぐだろうと考える。悲観論からではなく、それがもっとも自然だと思うからだ。それがいいかどうかは別にして。
「JUDO化」とは、競技スポーツ化によって世界の JUDO になった結果、日本のお家芸だった「柔道」がチカラを発揮できなくなってしまった現状を指している。
みなさんも、自分なりの結論を考えて見ると思考訓練になるので、やってみたらいかがでしょうか。具体的には、直接本文(P.141~142)をよく読んでみてください。
「⑥優良企業・優良人材脱出シナリオ」に対しては、国が制度面で規制撤廃を図っていく以外に施策はない。
なぜ私が、著者の見解にあえて反することをここに書くかというと、著者が
現状を憂えて主張する「べき論」と、日本人の特性と時代環境を踏まえた「である論」はわけて考えておきたいからだ。
現在の日本は、著者のみるように米国社会に近いといえる。ともに海外に出たがらない「ガラパゴス」の住民という点において。日本人も流動性が高かった高度成長期はもうウンザリだろう、落ち着きたいのだ。米国人も米国からさらによその国に移民しようというのは、一部のユダヤ系市民だけだろう。
ただし、
「膨張するガラパゴス」の米国に対して、
「縮小するガラパゴス」の日本という違いは存在するが。
しかし、同じマクロ経済データをみても、たとえば経済評論家の三橋貴明の所論とは正反対の結論にいたるのは面白いことだ。
書評 『日本のグランドデザイン-世界一の潜在経済力を富に変える4つのステップ-』(三橋貴明、講談社、2010)を参照。
著者は悲観的にものを見ているが、三橋氏は楽観的にみている。この違いはただ単にマインドセットの問題だけではないように思う。
日本はそのもてるマンガやアニメなどのソフトパワーによって、海外から観光客を「引き寄せ」ているという現実を無視すべきではないという視点をもっているか否かの違いではないだろうか。
実際にアキバ(秋葉原)にいってみればいい。外国人が多くいるのは、そこでしか入手できないモノが多数あるからだ。それは日本が、アキバこそが、お宝が無尽蔵にでてくる「ガラパゴス」だからである。
つまるところ、
日本全体の話と、企業や個人のとるべき選択肢は一緒に論じるべきではないのである。企業は株主の利害に従って、個人は自分のもてる資源とマインドセットに基づいて行動する。それだけではないか。
ただし、第3章の「脱ガラパゴスの道」で取り上げられた個別の業界とそこで活躍するプレイヤーである個別企業のケーススタディにあるように、要は非製造業においても、業界特性と製品特性を正確に把握したうえで、コンテンツを形式知化し、モジュール化をどこまで経営戦略に取り込めるかというミクロレベルの話なのである。
こういった戦略をとるかとらないかは、
あくまでも個別企業の選択の問題だ。
出版されてから8ヶ月たってから初めて読んでコメントするので、フェアじゃないかもしれないが、
この間に「ガラパゴス」の何が悪いのだという声も多数あがっているのは当然だと思う。amazonのレビューでも、そうじて本書の評価が低いのは、現在の日本の「空気」を体現しているといえる。
■
生物固有種の数においては、日本はガラパゴス以上の「超ガラパゴス」なのである!つまり「世界一」なのだ!
先日放送されていた、
NHKスペシャル「日本列島 奇跡の大自然 第2集 海 豊かな命の物語」では、生物固有種の数においては、なんと日本はガラパゴスに勝っている(!)そうだ。
日本は「ガラパゴス化」するどころか、そもそも日本こそ「超ガラパゴス」なのであったというオチがついたお話。
文明論の観点からいっても、いわゆる「鎖国」時代に、多種多様な独自の固有文化の花が開いたことは周知のこと。これが現在にまでつながる日本人の感性、発想のユニークさ(・・文字通りの one and only の意味で)を作り出しているのである。
だから、「ガラパゴス」であること自体はなんら問題はない。問題は、この「ガラパゴス」をいかにソフトパワーとして活性化するかにかかっているのではないか?
日本にしかいない「スノー・モンキー」(snow monkey)を見るために、外国から観光客がくる。スノー・モンキーとは、東北地方に住むニホンザルのことだ。これは、人間以外では、もっとも北に住むサルらしい。青森県はサル生息の北限である。
長野県の地獄谷温泉のニホンザルの映像はここ(YouTube映像)。
日本国内のエンジニアのモチベーションを維持するために、つねに難しい製品化開発に従事させているという実状も無視してはいけない。ただし、開発成果は自社内に埋もれさせず外販するなど、とるべき施策はいくらでもあるはずだ。死蔵されていまっている技術がかなり多い。
あとは日本のソフトパワーがどこまで米国のソフトパワーを凌駕できる所まで行けるかということにかかっているといえよう。すでにある
日本のソフトパワーの「引き寄せ力」には多大なものがある。ソフトパワーの中身そのものにかんしては、政府や官僚は余計なクチを挟むべきではない。個人や企業が活動しやすい環境整備に徹すればそれで必用にして十分だ。
浮き足立たずに、しっかりと自分の足元を見つめるべきだ。自分の会社も生き方も。
そもそも
「日本は・・」などと、国士きどり(?)の発言が空虚に響くのは、すでにそれが「昭和的」な風景と化しているからだ。「平成」に生きるわれわれは、まずわれわれ国民の一人一人が取り組まねばならないのは、自分とその家族、そして生活費を稼ぐ場である職場からだろう。
日本企業は、国内の厳しいマーケットと新興国のスペック要求の厳しくないマーケットを同時に攻略すればよい。ベンチャー精神に富んだ人は海外でもまれたらいいというお話だ。
海外に出たい人間は出るだろうし、
海外に出ざるを得ない人間もまた出るだろう。しかし、
出たくない人間はたとえ所得が下がっても、もはや移民という形でも出ようとしないだろう。
人口膨張傾向にあった過去の「近代日本」とは根本的に違うのだ。
これは、日本で暮らしている、ブラジルなどの日系人をみていると不思議ではないと思う。日本人は、ブラジル国籍の日系ブラジル人のことを「日本人」とはみていないと思われる。海外移民したら、あのようになってしまうのかと見ているのではないのだろうか。
日本人というのは、いったん日本から出てしまうと、糸が切れたタコみたいに縁が切れてしまいがちなのだ。中国人や韓国人とは違って宗族意識が弱いので、「一族内での世界ネットワーク」を形成しにくい。だから、華僑のような形での海外進出はあまり期待しない方がいい。
日本と海外を行ったり来たり、出たり入ったりしたらいいのではないかな。
<初出情報>
『ガラパゴス化する日本』(吉川尚宏、講談社現代新書、2010)のレビューは、このブログへの書き下ろしです。
目 次
第1章 ガラパゴス化する日本
ガラパゴス化とは何か?
日本製品のガラパゴス化 ほか
第2章 なぜガラパゴス化はよくないのか?
柔道とJUDO教訓
日本製品のガラパゴス化の行き着く先 ほか
第3章 脱ガラパゴス化への道
海運業界のケース
トレンドマイクロのケース ほか)
第4章 脱ガラパゴス化へのヒント
企業の新しい戦略遂行能力-ゲームのルールをつくる、ルールをかえる
霞が関商社化シナリオ ほか)
著者プロフィール
吉川尚宏(よしかわ・なおひろ)
A.T.カーニー株式会社プリンシパル。京都大学工学部卒、京都大学大学院工学研究科修士課程修了、ジョージタウン大学大学院修了(IEMBA プログラム)。野村総合研究所、野村総合研究所アメリカ・ワシントンDC支店等を経て現職。2009年10月より、総務省「グローバル時代における ICT 政策に関するタスクフォース」のメンバーに就任。専門分野は通信、メディア、金融サービス分野におけるマーケティング戦略、価格戦略、事業戦略、オペレーション戦略、制度設計や規制対応戦略など(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたもの)
PS 読みやすくするために改行を増やした。内容にはいっさい手は入れていない。(2014年8月12日 記す)
<ブログ内関連記事>
書評 『中古家電からニッポンが見える Vietnam…China…Afganistan…Nigeria…Bolivia…』(小林 茂、亜紀書房、2010)
・・新興国向けには過剰スペックではなく、ベーシックに高品質な製品を販売すべきだろう。メードインジャパンではなくなっても、日本ブランドがついている限り品質は安心できるというもので・・
書評 『空洞化のウソ-日本企業の「現地化」戦略-』(松島大輔、講談社現代新書、2012)-いわば「迂回ルート」による国富論。マクロ的にはただしい議論だが個別企業にとっては異なる対応が必要だ
書評 『この国を出よ』(大前研一/柳井 正、小学館、2010)
・・「この国をでよ!」と檄を飛ばすこの二人も、「いったんこの国をでたら戻ってくるな」などとは一言も言っていない。
書評 『民衆の大英帝国-近世イギリス社会とアメリカ移民-』(川北 稔、岩波現代文庫、2008 単行本初版 1990)-大英帝国はなぜ英国にとって必要だったのか?
・・
本国で雇用がつくりだせない以上、増大する失業者が社会問題にも発展しかねない。そこで活用されたのが、植民地だったのである
「JICA横浜 海外移住資料館」は、いまだ書かれざる「日本民族史」の一端を知るために絶対に行くべきミュージアムだ!
・・かつて過剰人口問題に悩んでいた日本もまた「移民」送り出しで問題解決を行っていた
書評 『未来の国ブラジル』(シュテファン・ツヴァイク、宮岡成次訳、河出書房新社、1993)-ハプスブルク神話という「過去」に生きた作家のブラジルという「未来」へのオマージュ
・・移民の国ブラジル。民族は共存し融合していく
書評 『日本文明圏の覚醒』(古田博司、筑摩書房、2010)
・・明治以来の「近代」は終わったんだよ、と静かに、しかし熱く語る論客の語りに耳を傾けよう。
『移住・移民の世界地図』(ラッセル・キング、竹沢尚一郎・稲葉奈々子・高畑幸共訳、丸善出版,2011)で、グローバルな「人口移動」を空間的に把握する
(2014年8月12日 情報追加)
(2012年7月3日発売の拙著です)

ケン・マネジメントのウェブサイトは
http://kensatoken.com です。
ご意見・ご感想・ご質問は ken@kensatoken.com にどうぞ。
お手数ですが、クリック&ペーストでお願いします。
禁無断転載!
end