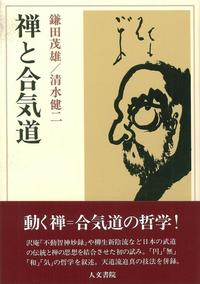このところ南方熊楠関連の本をひさびさに読んでいる。 南方熊楠は、粘菌研究を中心にして、森羅万象すべてに強い関心を抱いていた「知の巨人」である。わたしは大学時代から断続的に読んできた。
集中的に読んだのは2009年のことであったが、15年後の2024年の今回ひさびさに南方熊楠関連本を読むきっかけとなったのは、『熊楠 生命と霊性』(安藤礼二、河出書房新社、2020)である。
文芸評論家の安藤礼二氏は、ライフワークである『折口信夫』という大著で知られているが、最近その『大拙』を読んで大いに感心したので、積ん読のままになっていた『熊楠』も読んでおこうと思った次第。
安藤氏の『熊楠 生命と霊性』は、「粘菌・曼荼羅・潜在意識」/「神秘と抽象」/「生命と霊性」の3本の論文からなる。
最初の文章は別にして、のこりの2つは大拙がらみの熊楠というものであって、あくまでも「日本的霊性」を説いた大拙に熊楠を引きつけて論じている。そんな印象の強い内容であった。
その意味では、安藤氏の『熊楠』は『大拙』の副産物という位置づけと考えるべきであろう。まあ、森羅万象を論じた熊楠を論じるのはやっかいな仕事ではあるな。
熊楠は、あくまでも具体的な事物に関心が向かっており、思弁的な傾向はけっして強くない。安藤氏は、熊楠を買いかぶりすぎているようだ。読んでいて面白いのだが、はたしてそう言えるのかという疑問が生じる。 深読みが過ぎて、創作の領域に踏み込んでいるという印象だ。
安藤礼二氏は中沢新一系列の人なので、どうしても文学的想像力を駆使した飛躍が多いという印象を受ける。本人も「熊楠論」であって「熊楠研究」ではないと、断りを入れているのはそのためであろう。 あくまでも文芸評論家の「作品」と受け取るべきか。
*****
その「熊楠研究」の立場から、中沢氏系列の仕事に対して批判的な立ち位置にあるのが、『闘う南方熊楠 ー「エコロジー」の先駆者』(武内善信、勉誠出版、2012)である。
「熊楠研究」と「熊楠論」を区別するよう主張しているのがこの本だ。 武内氏の分類によれば、安藤氏の『熊楠』は「熊楠論」であり、安藤氏もそれを認めている。批判を謙虚に受け止めた結果である。
安藤氏は、『闘う南方熊楠』について上記の『熊楠』ではフェアな態度で言及しており、しかも武内氏の本には、南方熊楠と紀州田辺出身の合気道開祖の植芝盛平の関係も書いてあるようなので、さっそく取り寄せて確認してみることにした。
『闘う南方熊楠』は、和歌山市立博物館の学芸員という、「地の利」を活かした研究者による実証的な「熊楠研究」である。
新発見の資料などをもとに描かれた熊楠像は、実像に近い姿を描き出しているといえよう。「移民県」であった和歌山、そんな土地柄を知り尽くした人ならではの解釈は説得力がある。南方熊楠のような海外体験者は、当時の和歌山ではごろごろしていたのだ。
とくに「Ⅱ 在米民権運動とアメリカ時代の意味」「Ⅳ 神社合祀反対運動と「エコロジー」」が大いに読ませるものがある。このテーマには、むかしから大いに感心をもってきたからだ。
植芝盛平と南方熊楠が「神社合祀反対運動」において接触をもっていたことは、2代目道主・植芝吉祥丸の『合気道開祖 植芝盛平伝』でも触れられていた。 これは大学1年のときに読んで知っていた。
その事実が、本書のなかで、南方熊楠自身も書簡のなかで「植芝なる豪傑」について触れているという記述で裏付けられたことに、大いに満足感を覚えている。
というのも、こちらは安藤礼二氏好みのテーマであるが、鈴木大拙に与えたスウェーデンボルグの影響は、大拙による訳書をつうじて、これまた巨人というべき大本教の出口王仁三郎の霊界観にも大きな影響を与えているからであり、その王仁三郎と熊楠という両巨人と接点をもっていたのが植芝盛平だからなのだ。
合気道関係者は例外として、植芝盛平に対する関心をもっている一般人はそれほど多くないだろう。合気道を知らずに論ずるのは危険であることもあろうが、もっと植芝盛平の「思想」には関心をもってほしいと思っている。
*****
さて、話がそれてしまったが、安藤礼二氏の『熊楠 生命と霊性』が「熊楠論」であれば、武内善信氏の『闘う南方熊楠』は「熊楠研究」である。
後者はあくまでも研究者としての立ち位置を崩さす、前者は文芸評論家という立ち位置で事実関係をベースにしながらも、イマジネーションを駆使した作品と考えるべきだろう。 ある意味では、この2冊は補完的な関係にあるといってもいいかもしれない。
ただし、安藤氏にとっての熊楠は、折口信夫のようなライフワークではないので、どうしても折口論や大拙論に劣後するという印象は否めない。
熊楠は、大拙のような思想系の人物ではない。 森羅万象に関心を抱いていた南方熊楠だが、主要業績として現在に至るまで大きな意味をもっているのは「粘菌研究」であり、生物学者でもあった昭和天皇とあわせて顕彰すべき存在である。
なぜ熊楠が粘菌類を主要な研究テーマとしたのかについては、さまざまな見解があるが、熊楠在世当時の「進化論」を踏まえたうえで、考える必要があるという、安藤氏の指摘には耳を傾ける価値がある。武内氏の「進化論」にかんする言及は、通俗的見解に引きずられて不十分なようだ。熊楠のいう「エコロジー」は、ヘッケルの「エコロジー」そのものではない、と。
また、安藤氏が『近代論ー危機の時代のアルシーヴ』(NTT出版、2007)の段階でも指摘しているように、南方熊楠にかんしては「潜在意識」と「狂気と夢」にかんする安藤氏の指摘には無視できないものがある。この分野は、「予知夢」とからめて、また別途に探求する必要があろう。
南方熊楠は、わたしにとっては主要な研究テーマではないが、高校時代まで生物学に多大な関心を抱いており、小学生の頃から生物学者としての昭和天皇を尊敬してきたわたしにとって、熊楠は依然として親しみを感じる存在でありつづけている。
(画像をクリック!)
(画像をクリック!)
『闘う南方熊楠 ー「エコロジー」の先駆者』目 次はじめにー熊楠研究の動向と本書の目的Ⅰ 「明治」という時代とともに城下町和歌山と熊野「南方」という家、「熊楠」という名前城下町和歌山の学問・文化・教育と南方熊楠Ⅱ 在米民権運動とアメリカ時代の意味熊楠の渡米と自由民権在米民権新聞『新日本』からの手紙南方熊楠所持の条約改正反対意見秘密出版書アナーバーの回覧新聞『大日本』の再検討補論 南方熊楠対長坂邦輔―『珍事評論』の背景Ⅲ ロンドンから熊野の森へ孫文と南方熊楠南方熊楠における珍種発見と夢の予告「那智隠棲期」の検討Ⅳ 神社合祀反対運動と「エコロジー」南方熊楠と神社合祀反対運動神社合祀反対運動の始動と展開南方熊楠と世界の環境保護運動日露戦後の自然保護運動と「エコロジー」神社合祀反対運動における神社林と入会林「大逆事件」と運動の終局あとがき初出一覧南方熊楠の神社合祀反対運動関係年表索引
著者プロフィール武内善信(たけうち・よしのぶ)1954年和歌山県に生まれる。同志社大学大学院法学研究科博士課程後期満期退学。和歌山市立博物館主任学芸員、和歌山城文化財専門員。専門は日本近代史。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたもの)
<ブログ内関連記事>
(2023年11月25日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年12月23日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年6月24日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年11月19日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年10月22日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2020年12月18日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2012年7月3日発売の拙著です 画像をクリック!)
end