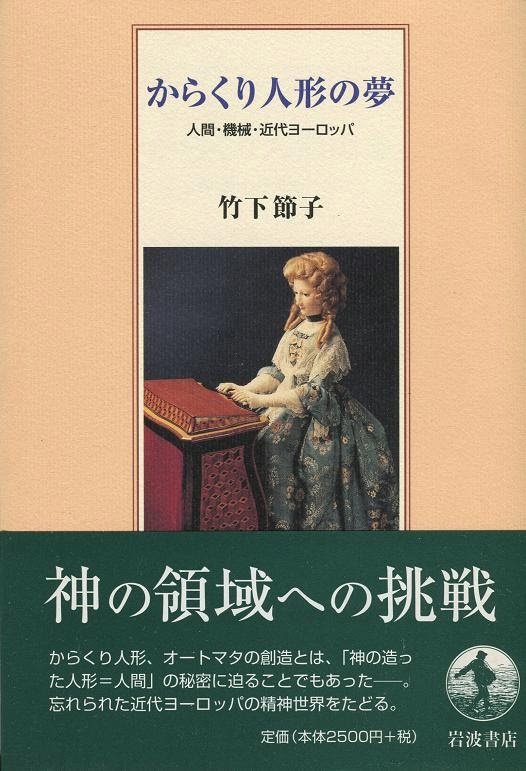2014年ソチ冬季オリンピック開催(2014年2月1日~23日)と重なってしまったため、すでに記憶から消えてしまっているかもしれませんが、
ローザンヌ国際バレエコンクール最終選考で日本人が一位と二位を独占したというニュースが話題となったことを思い起こしてほしいと思います。
ローザンヌで優勝した17歳の男子高校生の二山治雄さんは、
オリンピックの男子フィギュアスケートで金メダルを獲得した19歳の羽生結弦選手と重なり合わせてみてもいいかもしれません。
フィギュアスケートが氷上のバレエといわれることも多いことから、それはけっして突飛な連想でもないでしょう。この二人の男子は年齢が近いだけでなく、意外なことに、いずれもそれほど長身ではありません。
よく伸びた手足に小顔なので長身に見えますが、羽生結弦選手は身長171cm、二山治雄さんは公表数字はありませんが、
「世界に挑む 若き日本人ダンサーたち~第42回ローザンヌ国際バレエコンクール~」(NHK 2014年2月16日放送)というテレビ番組でバレエ関係者がしていたコメントでは、170cm前半とありました。
西洋人にくらべると体格面で劣っているのは否定できませんね。
ローザンヌのバレエ・コンクールにかんして、面白いコメントが目にとまったので紹介しておきたいと思います。新聞社のサーバーから記事が削除される可能性もありますので、全文を引用しておきましょう。
【ローザンヌバレエ席巻】体形と意欲、日本人向き こつこつと技術習得 (MSN産経ニュース、2014年2月2日)
ローザンヌ国際バレエコンクールは、2年前の2012年にも当時17歳の菅井円加(すがい・まどか)さんが優勝するなど日本人バレエダンサーの躍進が目立つ。
背景には、跳躍など一つ一つの技を高いレベルでこなす技術力が指摘されている。 舞踊評論家の佐々木涼子さん(69)は「基本からしっかりと積み上げた技術力が極めて高い水準に達している」と分析。「一般的にバレエは優美なイメージが強いが、実は技術の優劣がはっきりと出る踊り。こつこつと技を磨く日本人の性格に向いている」と話す。 40年以上バレエ指導に携わる法村(ほうむら)友井バレエ団(大阪)の法村牧緒団長(68)は、「日本人は欧米人に比べて小柄で手足も短い分、重心をコントロールしやすく、難しい技を身につけやすい」とし、日本人の体形が、技術向上に一役買っていると指摘する。
日本人ダンサーは練習意欲も際立っているといい、法村さんは「国内でもコンクールが盛んで、勝つために技を磨く意識が非常に高い」。二山治雄さんが日本人男性として1989年の熊川哲也さんと並び優勝を果たしたことで、「男性のバレエも勢いが増していくと思う」と期待を込めた。(* 太字ゴチックは引用者=さとう)
「日本人は欧米人に比べて小柄で手足も短い分、重心をコントロールしやすく、難しい技を身につけやすい」、という指摘が興味深いですね。
とくに
「重心をコントロールしやすく」という指摘は、
基本的に日本の武道と同じです。
■
「軸を中心にした回転運動」
個人的な話になりますが、いまから20年以上前、アメリカの大学院に留学中にボランティアでアメリカ人大学生たちに合気道(Aikido)を指導していたことがあります。
その経験をつうじてわかったのは、
白人も黒人も一般的に下半身の股下が長く、重心をコントロールしにくいということ。
重心(center of gravity)は、武道では「臍下丹田」といって
へそ下三寸にあるとされていますが、
脚が短いほうが重心が低くなるのでコントロールしやすいことは否定できません。これは大相撲の外人力士、とくに欧州出身の力士を観察していれば理解できることだと思います。すり足で動く相撲では、重心が高いと安定感を欠くのです。
フィギュアスケート、バレエ、そしてと合気道をはじめとする日本武道。西洋のパフォーミングアートであるバレエ、東洋の武道。華やかな前者と地味な後者。いっけんまったくかけ離れていますが、
身体運動でかつ回転運動を基盤に置いているという点にかんしては共通性があります。
そもそもスポーツはすべて軸を中心とした回転運動が基本にありますが、フィギュアスケートやバレエ、そして武道ほど、実際に自分がやっていないとしても、目に見える形で現れますので、観察して実感することができるといってよいでしょう。
バレエとの対比においては、東洋の伝統舞踊にも言及しておく必要があります。
カンボジア王国のシハモニ国王は、シハヌーク前国王から皇太子に指名されるまで、
フランスのパリで20年以上にわたってバレエ教師の職についていたことは東南アジア通なら常識でしょう。カンボジアに帰国後には、クメール舞踊協会の代表をつとめていました。クメールとはカンボジアのことです。
カンボジアがフランスの植民地であったこと、シハモニ国王の母親がフランス系カンボジア人であることは多少は関係があるかもしれません。シハモニ王子が、なぜバレエの道に進んだのか詳しいことは知りませんが、当時は社会主義圏にあったチェコのプラハでバレエを学んだようです。
優美なクメール舞踊はインド舞踊やタイダンスと同様、じっさいにやってみればわかると思いますが、手の返しがひじょうにむずかしい。伝統舞踊は子どものときに必修として教育されているようですが、そうでなければ大人になってからは習得は困難でしょう。
タイの国技ムエタイは白兵戦で戦うために開発された武術ですが、ムエタイの試合前には優美な舞踊が披露されます。蹴りを中心にしたムエタイは、バレエなみのカラダの柔軟性が基本にあります。
むかし、合気道の師匠である有川定輝先生からお聞きしたことですが、日本の武道の源流はインドにあるのだ、と。
インドから中国を経由して日本に入ってきた点は、武道は仏教と共通しています。
■
バレエと合気道
話を日本の武道に戻しましょう。武道のなかでバレエともっとも近いという印象をもつのが合気道でですね。
バレエと合気道の関係については、
バレエの世界から合気道の世界を経て、独自の「呼吸法」を開発して普及につとめている西野皓三氏の存在を想起すべきでしょう。そして西野氏の弟子でバレエ時代からずっと従ってきた弟子の由美かおるの存在も(写真上下)。
合気道だけではありません。
柔道も、空手もみな軸を中心にした回転運動が根底にあります。柔道の投げ技、空手の回し蹴りを想起してみればいいでしょう。ともに
軸足を支点にした回転運動です。
合気道開祖の植芝盛平翁のもとには、日本舞踊関係者などが多く入門して、その秘訣を学ぼうとしていたそうです。
合気道も日本舞踊もすり足を基本にしています。すくなくともこの事実から、
武道と舞踊の密接な関係については理解できると思います。
武道というコトバができる以前は「武芸」といわれていたことも、
本質において「芸」としての共通性があることが示唆されています。能や歌舞伎などと同じく、「芸」としての共通性ですね。
合気道においては、「呼吸法」がきわめて重要な意味をもちます。さきに武道と仏教はインドから発して中国経由で日本に伝来した点に共通性があると言いましたが、「呼吸法」にかんしても、ヨーガの呼吸法が禅仏教をつうじて中国から日本に伝わったことの意味も大きいものがあります。禅の呼吸法は、言霊(ことだま)学をつうじて合気道に多大な影響を与えている、古神道(こしんとう)の呼吸法にも影響を与えているのでしょう。
わたし自身はバレエをやった経験はないので、バレエの観点からの話はできませんが、バレエと合気道の関係について、西野皓三氏と由美かおる氏の対話を手掛かりに考えてみたいと思います。
■
西野皓三氏と由美かおるの対話から
『西野式呼吸法 バイオスパーク』(由美かおる、講談社、1985)という本があります。由美かおるが、その師である西野皓三氏の「西野式呼吸法」を解説した内容の本です。
いまから30年近く前に出版された本で、すでに絶版で入手できませんが、たまたま蔵書整理していた際に「再発見」しました。パラパラとめくって読んでいたら、ひじょうに興味深いことが書いてあることに気がつきました。
第3章「西野式呼吸法はこうして生まれた」は、由美かおるがその師匠である西野皓三に話をうかがうという形で、「西野式呼吸法」誕生に至る経緯が西野皓三氏のライフヒストリーに沿って説明されています。
人体の構造について熟知している医学生だった西野氏が、
バレエから初めて合気道を経て、中国拳法を習得し、独自の「呼吸法」に到達した経路が、下図においてよく表現されています。この
3つに共通するものが「呼吸法」なのです。
(西野式呼吸法は西野皓三氏のライフヒストリーそのもの P.46より)
西野氏はわたしも教えを受けた合気会で師範もされていたこともあり、壮年時代の西野氏が合気会で段位をとっていた由美かおるの受けをとる演武は、ずいぶん昔のことですが武道館で見たことがあります。
西野皓三と由美かおるの対話から重要な点をいくつか抜書きしておきたいと思います。太字ゴチックの個所は、いずれも引用者(=さとう)によるものです。
由美 先生は日本人だから、当然のこととして、西欧のバレエから日本の舞や武道に戻ってきたわけですね。
西野 戻ってきたというよりは、広がってきたという感じだろう。バレエの動きが内から外へぐんぐん広がっていくのとは対照的に、日本の動きは内に秘められた微妙さが重要になるのだが、武道に、そうした日本の動きのもつ原点がいくつも含まれている。・・(中略)・・ そんなわけで、日本の動きをぼくは合気道で学ぼうと思った。合気道を始めてよかったと思う。
その後、西野氏は中国拳法も習得しています。
西野 合気道で、日本古来の武術の技の粋と心を学び、争わざる心を培われ、そして、中国拳法では澤井(健一)先生によって、中国古来の内攻の力(体の奥底から出る力)を使った武術の強さを教えられた。太極拳の高弟たちの強さは群を抜いている。
体の柔らかさと呼吸の関係についてはこう述べています。
西野 双葉山も柔らかくて、美しい力士だった。柔らかいということは当然呼吸と深い関係がある。それに美しいということ、これは何をやるにも大事なことで、特に体を使う表現で美しくないものはまずダメだ。
「ねじる」ということに論が及ぶ。ここから先が本題です。バレエ、合気道、中国拳法の比較論が展開されています。長くなりますが、じっくり読んでいただきたいと思います。かならず「発見」があるはずです。
由美 そういえば、バレエのねじりはすごいですね。
西野 バレエは、空間を制覇した芸術だといわれている。近代バレエが本格的に完成したのはアン・ドールという決定的なねじりができ上がってからだ。アン・ドールは両足を180度開くポジションのことだが、これが完成するまでに200年かかっている。
由美 そんなにかかっているんですか。バレエのねじりには他に、アン・ド・ダンというのもありますね。
(西洋のバレエと日本の武道の中間に中国武術がある P.60より))
西野 アン・ドールが外側(遠心的)に開くのに対して、内側(求心的)にねじることがアン・ド・ダンだ。この二通りのねじり方は太極拳でも合気道でも、一応完成された動きには必ずある。使い方や動きの意味はそれぞれ違うが、体を外側、内側にねじるといった動きの根本は同じだ。・・(中略)・・ 合気道では外にねじる動きは転換(てんかん)で代表され、内にねじる動きは入身(いりみ)に代表されるといっていいだろう。
由美 私も何となく、太極拳と合気道の流れるような動きが似ていると思っていました。
西野 ただ、同じねじりといっても、それぞれに特徴がある。バレエは背筋をスッと伸ばし、腕や脚を大きく開いて外に外に広がる遠心的なもので、日本の舞いや武道の動きは、肘や膝を内へ内へと向ける求心的なものだと思う。もちろん、バレエにも求心的な動きがあり、日本の舞いや武道にも遠心的に動くものがあるが、根本的には西欧は外、日本は内という感じだ。そして、中国拳法(太極拳や形意拳など)の動きは、ちょうどその中間のような気がする。
由美 地理的にも真ん中にありますものね。
(バレエと中国武術の近似性 P.62より)
洋の東西によって身体運動の基本的方向性が異なるものの、基本は共通していることが確認されたと思います。
バレエと合気道の中間に中国拳法(=中国武術)を置いてみると、共通性がくっきりと浮かび上がってきますね。上に掲載した図を、じっくりと眺めてみるといいでしょう。
わたしが大学時代に合気道を教わった有川定輝先生は、
中国武術は日本武道よりもはるかにカラダの柔軟性が要求されると語っていました。
インド武術は中国武術よりもさらに柔軟性が要求されるのだ、と。インドを中心においてみえると、身体運動の観点からみれば、バレエと中国武術が対応しているといえるかもしれません。
このように考えてくると、
いっけん関係ないと見えるバレエと合気道の関係も見えてくるでしょう。まずは
基本的な「型」(パターン、ポジション)の習得からはじまり応用に進むという共通性をもちながらも、相
違点は主たる運動の方向性と柔軟性の度合いにあることがわかりますね。
■
日本人の身体という「制約」を逆手に取る
日本人のフィギュアスケーターも、バレエだけでなく合気道にも目を向けてみたらいいのではないでしょうか。日本人のバレエダンサーも、合気道などに目を向けるべきではないでしょうか。
野球の世界では、
王貞治氏や広岡達朗氏が合気道の修業をつうじて「野球道」を探求していたことは知られています。
桑田真澄氏も、古武術の甲野善紀氏の教えをフォーム改造に応用しています。アメリカのベースボールが、日本の野球として定着するプロセスにおいて、このような取り組みがあったことを想起することも必要でしょう。
メジャーリーグで現役をつづけている
イチローもまた、低い重心の中心軸をつくるため、相撲の四股(しこ)のようなスタイルで下半身を強化しいます。テレビでヤンキーズの試合を見るときにはぜひ注目してほしいと思います。
日本人は、日本人の身体という「制約」から完全に脱することが不可能である以上、
むしろそれを逆手に取って日本人であることを徹底的に深掘りしてみることが大事ではないでしょうか。徹底的にフィギュアスケートやバレエのテクニックを身に付けたうえで、さらに日本伝来の身体運動に目を向けてみる。壁にぶちあたったときには、かならず試みてほしいのがこういった取り組みです。
日本人がスポーツという西洋文明の粋のなかで活動するためには、意識して取り組むべき課題ではないでしょうか。教育学者の斎藤孝氏は、
「腰・ハラ文化の再生」が必要だと、『身体感覚を取り戻す-腰・ハラ文化の再生-』(NHKブックス、2000)において主張されています(*注)。耳を傾けるべき主張だと思います。
もちろん、これはスポーツに限らず、
現代文明を生きる日本人すべてにとっての課題であるというべきでしょう。「足元を掘れ、そこに泉あり」、というではありませんか!
自らのうちなる日本を意識することがあたらしい時代を開くカギなのです。
(*注) 本文の最後で触れた
『身体感覚を取り戻す-腰・ハラ文化の再生-』(NHKブックス、2000) については、いまから13年前の2001年に ネット書店の bk1(・・現在は honto)にわたしが書評を書いていますので、ここに再録しておきます。
この本は、斎藤孝氏が脚光を浴びるキッカケになった本で、原点とでもいうべき内容の濃い一冊といってよいでしょう。
■本書はまさに警世の書である!「失われた10年」よりもっと深刻な事態が進行しているのだ (投稿者:サトケン)
日本人が椅子の生活を始めてから、たかだか30年しかたっていない。それまでずっと続いていた、畳に座り、胡座(あぐら)をかき、正座する生活においては、腰・ハラは自然と鍛えられていた。「失われた10年」というフレーズがあるが、それよりもっと深刻な事態が進行しているのだ。高度成長によって日本人の生活が激変したことと、従来からあった身体感覚の喪失はパラレルに観察される現象だ。
本書はまさに警世の書である。日本の腰・ハラの身体文化の衰退とともに、「練る」「磨く・研く」「締める」「絞る」「背負う」といった日本語の基本動詞が失われつつあることに、著者は大きな注意を喚起している。日本人の精神性を規定してきたこれらのコトバが失われることは、日本人のアイデンティティが崩壊することを意味してもいる。現在の日本人は国際的に自己を確立しなければならないというのに、日本人としての軸を欠いたまま漂っていくのみでは、国際社会で尊敬されるハズがないのも当然だ。
欧州を旅行してとにかく目立つのが日本人の姿勢の悪さである。欧米人は老人と子ども以外、男も女も関係なくみなピシっと背中を伸ばして歩いている。これは彼らが日本国内で歩いているときも同じである。一度かれらの歩く姿をじっくりと観察していただきたい。日本人の姿勢の悪さは、精神のたるみに対応しているといわざるをえない。生活が洋風化したから姿勢が悪くなったのではないのだ。昔の日本人の姿勢がよかったことは、本書に収められた幕末や明治初期の写真からもうかがわれる。
ぜひ本書を読んで問題の深刻さに気づき、自らの姿勢を(もちろん物理的に!)正すことから、まず意識改革の第一歩を踏み出して欲しい。著者は1960年生まれの教育学者で、本書は年寄りの繰言ではない。 (投稿: 2001年3月28日)
<関連サイト>
西野式呼吸法 (公式サイト)
バレエダンサーとしての西野皓三(27歳)
・・写真でみる若き日の西野皓三氏
<ブログ内関連記事>
「ブレない軸」 (きょうのコトバ)
「軸」がしっかりしていないと「ゆがみ」が生じる-Tarzan No.587 「特集 軸を整えて、ゆがみを正す」(2011年9月8日号)
『鉄人を創る肥田式強健術 (ムー・スーパー・ミステリー・ブックス)』(高木一行、学研、1986)-カラダを鍛えればココロもアタマも強くなる!
・・「中心軸」の重要性を語って止まなかった肥田春充(ひだ・はるみち)
合気道・道歌-『合気神髄』より抜粋
カラダで覚えるということ-「型」の習得は創造プロセスの第一フェーズである
書評 『正座と日本人』(丁 宗鐵、講談社、2009)-「正座」もまた日本近代の「創られた伝統」である!
・・「正座」はやらないほうがいい
書評 『日本力』(松岡正剛、エバレット・ブラウン、PARCO出版、2010)-自らの内なる「複数形の日本」(JAPANs)を知ること
バレエ関係の文庫本を3冊紹介-『バレエ漬け』、『ユカリューシャ』、『闘うバレエ』
コトダマ(きょうのコトバ)-言霊には良い面もあれば悪い面もある
・・山岸涼子のバレエマンガ『言霊』を取り上げている
【セミナー告知】 「異分野のプロフェッショナルから引き出す「気づき」と「学び」 第1回-プロのバレエダンサーから学ぶもの-」(2012年11月29日開催)
【セミナー終了報告】 「異分野のプロフェッショナルから引き出す「気づき」と「学び」 第1回-プロのバレエダンサーから学ぶもの-」(2012年11月29日開催)
書評 『人種とスポーツ-黒人は本当に「速く」「強い」のか-』(川島浩平、中公新書、2012)-近代スポーツが誕生以来たどってきた歴史的・文化的なコンテクストを知ることの重要性
(2023年11月25日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年12月23日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年6月24日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年11月19日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年10月22日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2020年12月18日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2020年5月28日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2019年4月27日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2017年5月19日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2012年7月3日発売の拙著です 画像をクリック!)
ケン・マネジメントのウェブサイトは
ご意見・ご感想・ご質問は ken@kensatoken.com にどうぞ。
お手数ですが、クリック&ペーストでお願いします。
禁無断転載!
end