仕事の関係の本ばかり読むことを余儀なくされていると欲求不満がたまってくる。必要だから読むのだが、かならずしも「楽しみのための読書」ではないからだ。
大きな仕事から解放されたので、読みたかった本をやっと読むことができるようになった。 『妖怪少年の日々-アラマタ自伝』(荒俣宏、角川書店、2021)。
ことしの1月の新刊本。二段組みで467ページのボリュームだが、あっという間に(・・といっても物理的制約から一気読みはできないが)読んでしまった。
といっても、興味のない人には、まったく面白くともなんともないだろう。1980年代から荒俣氏の作品(著作や図鑑・・)に触れてきたわたしにとっては、ぜひ読みたい1冊だった。TVの怪奇番組などのコメンテーターとして出演していたので、知っている人も少なくないと思うのだが。
帯には、「知の巨人・荒俣宏はいかにして形づくられたか? 人生の軌跡を網羅した初の自伝」とある。 たしかに荒俣宏氏は巨体なので「知の巨人」という表現は間違ってないが、「知の怪人」といったほうがピッタリくるのではないかな。博覧強記の作家で博物学者の荒俣宏氏は、現代の南方熊楠というべき怪人だ。
ことし74歳になるアラマタ氏も「自伝」を書くような年齢になったのか、という感慨がある。これもまた「終活」の一つなのだろう。寂しいといえば、寂しい話ではあるが。
狂気にまで近い収集癖と蔵書量と、そこから生み出される膨大な作品で読者を圧倒してきた人だが、そんなアラマタ氏も蔵書はほぼすべて整理して、人生最後のプロジェクトである「妖怪と生命のミュージアム」(所沢市)に集中しているそうだ。
「自伝」と銘打たれているが、人生の軌跡を語りながらも、脱線につぐ脱線で、それじたいが面白い。とはいえ、長年の読者としては知りたいことが大幅に漏れているという感想もなくはない。これとは別にインタビュー形式での「自伝」も必要だろう。
帯のウラには、「数多くの「師匠」たちとの出会いから、知の巨人の脳内を紐解く」とある。そこにあげられているのは、平井呈一、紀田順一郎、平田弘史、石ノ森章太郎、エドガー・アラン・ポー、渋澤龍彦、そして水木しげるーー。」
「妖怪」つながりの水木しげるとの関係は比較的知られているかもしれないが、著者にとってもっとも重要な師匠は平井呈一氏であり、紀田順一郎氏であることが、この自伝のはしばしから浮かび上がってくる。10代の少年時代から多大な影響を受けてきた人たちだからだ。
平井呈一はラフカディオ・ハーン全集の個人訳を完成した人で、英語の怪奇小説・幻想小説翻訳の第一人者で日本語の達人。荒俣氏が中学生のときに弟子入りし、その縁で紀田順一郎氏を紹介されている。
紀田順一郎氏は、1980年代から「知的生産」の実践家で多くの仕事をした人だが、荒俣宏氏にとっては兄弟子にあたるような人だ。60年近い交友の記録は読んでいて気持ちいい。
紀田順一郎氏も名だたる蔵書家であったが、現役を退き「終活」のため泣く泣く蔵書を手放している。その経緯は『蔵書一代-なぜ蔵書は増え、そして散逸するのか』(松籟社、2017)に書かれている。
わたしは高校時代から紀田順一郎氏の本を読んできたが、おそらく最後の本であろうこの本は、何度も繰り返し読んでしまう哀切きわまる文章が冒頭に収められている。
そんな紀田順一郎氏について、荒俣氏はこう語っている。出会って最初の頃の回想だ。
紀田先生を知って、もっとも刺激を受けたのは、その幅広い関心分野だった。紀田先生の口癖は、「読書するなら古典と同時に尖端・前衛をあわせて読みなさい。どっちが欠けてもダメですね」であった(P.236)。
まさに至言というべきだろう。
紀田、荒俣の両巨人には及ぶべくもないが、わたしもこの方針で本を読んできた。若き日の荒俣氏は、紀田氏のすすめで『利根川図誌』や『北越雪譜』を読むことになったそうだが、平田篤胤だけではないのである。紀田氏とは関係なく高校時代からこれらの本に親しんできたわたしも、おおいに共感を感じるのである。
内容が盛りだくさんの本で、面白いのでどんどん先を読みたくなってくる。だから、大きなプロジェクトを抱えているときは、手出しはしないほうがいい。そんな本であった。
(画像をクリック!)
<ブログ内関連記事>
(2023年11月25日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年12月23日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年6月24日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年11月19日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年10月22日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2020年12月18日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2012年7月3日発売の拙著です 画像をクリック!)
end


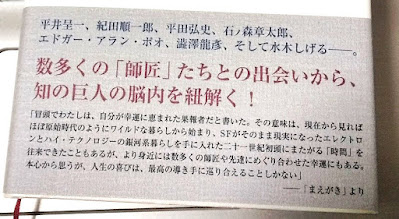






















.jpg)






























