「水問題」解決のためのソリューションこそ、イスラエルの最大の成果であり、これこそが今後の人類社会にとって最大の貢献となりうる。
この本を読まずにイスラエルについて語ることはできないと、つよく感じている。
というのは、ものごとにはすべて正負の両面があるが、2023年の「10・7テロ」以来、ふたたびイスラエルのネガティブな側面が前面にでてしまったからだ。
1,400人が殺害された凄惨な無差別テロへの報復として始まった、無慈悲なまでの爆撃によるガザ地区への攻撃。ハマスの戦闘員を含めたパレスチナ人の一般人の死者が、すでに2万人近くになっている。
イスラエルの国際的なレピュテーションは地に落ちてしまった。国家ブランドは毀損(きそん)してしまったのである。
信頼が回復されるまで長い時間が必要だろう。どんなに脳天気な人間でも、さすがに手放しで礼賛するのは避けようとするに違いない。
イスラエルがこの状態から脱するには、軍事や戦争とは関係性の低い「民政分野での貢献」で国際的な信用を回復することが求められる。たとえ、それが地味であっても、地道で息の長い協力が必要だ。
だからこそ、イスラエル人の長年の汗と知力の結晶ともいうべき、水問題解決のソリューションで国際貢献を推進すべきなのだ。
■人間の生存に水は不可欠。国家の生存に水は不可欠
人間にとっては、水がなければ生存すらおぼつかない。これは断食を体験してみればすぐにでもわかることだ。水だけでも、人間は数日なにも食べなくても大丈夫である。
もちろん、水だけでは人間は生存できない。とはいえ、食物となる動植物も水が必要不可欠だ。土があっても、水がなければ作物は栽培できないのである。植物がなければ動物も生存できない。食物連鎖の最上位にある人間にとっては、言うまでもない。
都市や国家を維持するために水がいかに重要か、これは歴史が示している。
水の重要性を熟知していたからこそ、高度な土木技術で水道を建築したのがローマ帝国であった。身近なところでいえば、玉川上水の掘削によって百万都市江戸を支えたのが徳川幕府であった。
ただし、これらはみな水には恵まれた地域に誕生した国家であった。
イスラエルは、国土の大半が砂漠という恵まれない土地である。だからこそ、建国以前から、ベングリオンをはじめとする入植活動のリーダーたちは、将来の人口増大を支えるため、いかにして水を確保するかを重要なテーマとして捉えていたのである。
日本のような水に恵まれた国でも「節水」が呼びかけられているが、イスラエルにおいては、「節水」は国家安全保障そのものといっていい。
社会主義経済として始まったイスラエルだが、冷戦崩壊後の規制撤廃による自由化で1990年代以降に資本主義経済化が進展したあとも、水だけは国家管理が徹底しており、水問題を政争の具につかえないよう、政治介入を回避する制度的な仕組みが確立している。
「水の一滴」もムダにしないこと、これが幼時の頃から徹底してたたき込まれるのである。しかも「節水」だけでなく、排水や汚水をいかに再利用し、豊富な海水をいかに淡水化して利用するかも課題となってきた。
およそ水にかんする、ありとあらゆる問題解決にチャレンジしてきたのがイスラエルである。国家としてのサバイバルのために不可欠だったからだ。
■イスラエルが生み出してきた水問題解決技術
水問題の解決のため、イスラエルが生み出してきたソリューションには以下のようなものがある。いずれも現場で発生している問題を、机上の空論ではなく、あくまでも実学として現実的に取り組んできた成果である。
節水の観点から重要なものは、まずは農業テクノロジーの分野における「点滴灌漑」をあげるべきであろう。
わずかな水をムダにすることなく、効率的に農作物を栽培するための画期的な技術である。基本的にローテクだが、発想がすばらしい。流量調整が可能で、施肥も灌漑によって行うことが可能となる。
また、生活排水を再処理してリサイクルし、「再生水」を農耕用に確保することを可能としただけでなく、水パイプラインの敷設によって砂漠を農地に変えることに成功してきた。
廃水処理は地下水の汚染をふせぐことにつながり、また土地の「塩害」や「砂漠化」を防ぐための取り組みも積極的に取り組んできた。
「逆浸透膜」をつかって海水を真水に変える技術も開発し、海水から塩分を除去するプラントが建設されている。地中海や紅海に面したイスラエルにとって、海水は豊富に存在する水資源であり、これをつかわない手はない。
さらに、こういった水問題解決のソリューションは、IT化と合体することでパワーアップしている。集中管理センターでのモニター管理が可能となり、たとえば水道管の漏水の早期発見と対応が可能となっている。漏水は節水の敵である。道路陥没の原因でもある。
このほか水関連のさまざまな分野で DX化(=デジタル・トランスフォーメーション)が進展していることに注目すべきであろう。IT分野での先進国イスラエルならではというべきだ。
水問題解決のソリューションは、従来は国家主導で行ってきたが、経済自由化後の現在では国家機関はテクノロジー・インキュベーターとしての役割をはたし、水関連技術のニッチ分野での民間のスタートアップの参入を促がしてきた。
この結果、イスラエルでは各種の「ウォーター・ビジネス」が誕生し、さらには技術輸出によるグローバルな「水市場」の創出に成功している。国内市場の小さなイスラエルとしては理想的な展開である。
水に恵まれた日本人には想像しにくいが、水不足に起因する衛生問題など、水問題に苦労している人びとは世界中でひじょうに多いからだ。しかも、気候変動と環境問題の悪化で、水を求めて「難民」も発生するようになってきている。
建国後の早い時期からのアフリカ支援に加え、国家承認を避けられてきたインドや中国といった大国との関係構築が可能となったのも、水関連ソリューションのおかげである。日本人が知らない世界がそこにある。
水問題にかんしては、日本はイスラエルとは違った意味で水道が危機的な状況にある。この現状を踏まえたうえで、日本人も水問題に主体的な関心をもつことが必要だ。
■米国とイスラエルが密接な関係になった背景にも水問題
トルーマン大統領が議会の反対を押しきって、いちはやく独立直後の1948年にイスラエルの国家承認を行ったことが、米国との密接な関係の始まりにあるとされている。
米国がイスラエルとの関係を深化させたのは、1960年代に入ってからだ。「第3次中東戦争」(1967年)では、それまで武器を供与してきたフランスが親アラブ政策に転じたため、代わって米国が軍事援助を行うようになって現在に至っている。
だが、それだけではない。ケネディ大統領暗殺後に副大統領から昇格したジョンソン大統領は農村出身であり、水問題に対する関心の深さにかんしては、イスラエルの政治指導者と問題を共有していたことも大きい。
ニクソン政権になってからは、水問題における重要性が劣後したようだが、環境問題の悪化で水不足に転じたカリフォルニア州を中心に、水問題のソリューションをつうじたイスラエルとの関係も重要性を増してきている。
米国のような先進国もまた、水問題を避けて通れなくなっているのである。
■水問題の解決こそ地域安定化のためのカギ
水問題の解決こそ地域安定化のためのカギである。イスラエルにとっては、とくに近隣のヨルダンとパレスチナの安定が重要である。
ヨルダン川を挟んで東岸で隣接するヨルダン王国とは、水管理の点からも密接な関係を構築している。水源となるヨルダン川と死海は両国の共同管理である。
パレスチナ自治区においても、ほぼ100%に近く水道が敷かれている。この事実は知っておくべきだろう。国連決議を無視して行われているユダヤ人入植地だけでなく、ヨルダン川西岸のパレスチナ自治区全域においてのことある。
ただし、イスラエルが管理する地区と、自治政府が管理する地区ではメンテナンス面などにおいて違いがでているようだ。水泥棒に対する警察権の行使にも違いがでている。
「10・7」テロ後に水や燃料などがストップされ危機的状態になっているガザ地区だが、ハマスが実効支配するガザ地区では、西岸とは違って、はるか以前から水問題が深刻な状況にあったことが本書をよむとわかる。イスラエルが2005年にガザ地区から撤退後、ハマスはイスラエルとの協力を拒んできたからだ。
ガザ地区の深刻な水問題とは、地下水くみ上げによる枯渇、廃水による土壌汚染、汚染水の垂れ流しによる地中海の海洋汚染などである。水問題という観点から、人口増大への対応を行ってきたハマスの責任はきわめて重い。
軍事的手段による「ハマス排除」がいつ、いかなる形で完了するのか現時点ではわからないが、戦争終了後にはイスラエルは民生面で「ガザ地区再建」の責任を果たさなくてはならない。これは当然の責務である。国際社会の目を意識してもらいたい。
さらにいえば、長期的な展望として、水問題の解決がイスラエルとその周辺地域の安定化に貢献することを期待したい。いかなる体制になろうと、共存共栄のための大前提が、水の確保と水問題の解決にあることは、イスラエル自身の経験からも明らかである。
政治面だけではなく、水問題解決という点から地域安定化のカギを見いだすことが可能ではないだろうか。関係者がみな、冷静に考えることが必要であろう。
■「イスラエルによる水問題解決の歴史」と題すべき内容
イスラエルによる水問題解決への取り組みの全体像を知るうえでは、きわめてすぐれたノンフィクションである。
技術関連の説明が少なく、「人工降雨」技術については数行だけで済まされていたのが残念ではあるが(・・イスラエルは2021年以降は人工降雨は実行していないようだ)、じつによく調べて、しかも整理して書れており読み応えがある。同族としての共感と適度な距離感を維持している、ユダヤ系米国人ならではのイスラエル理解である。
日本語タイトルは、原著タイトルの Let There Be Water: Israel's Solution for a Water-Starved World と同様に、イスラエルは副題に隠れてしまっているが、内容的には「イスラエルによる水問題解決の歴史」とでもすべきである。
水が豊富な日本とは真逆のイスラエルは、水に乏しいという「逆境」を逆手にとってサバイバルしてきた。国際関係は、政治だけを見ていただけではわからない。ビジネスと経済、そして技術の視点が不可欠なのである。
『水危機を乗り越える!』は、水問題に関心のある人は言うまでもなく、イスラエルに関心のある人も読むべき本である。英語版でもいいと思ったが、専門用語が多いので日本語訳で読んだほうがいいかもしれない。訳文は正確で読みやすい。
目 次はじめに 人口 中流階級の台頭 気候変動 汚染水 漏水 世界のソリューションモデル第1部 水資源立国への道第1章 水を敬う文化第2章 水は国が管理する第3章 給水システムを経営する第2部 水を生産する第4章 したたる水で作物を育てる第5章 廃水をふたたび水にもどす第6章 海水を真水に変える第7章 豊かな水の国に第3部 国境を越える水問題第8章 グローバルビジネスとなった水第9章 水の地政学―イスラエル、ヨルダン、パレスチナ第10章 水の外交―中国、イラン、アフリカ諸国の場合第11章 豊かなはずの国の水危機―ブラジル、カリフォルニアの場合)第4部 イスラエルのソリューション第12章 水の哲学謝辞訳者あとがき原註インタビュー一覧参考文献
著者プロフィールセス・M・シーゲル(Seth M. Siegel)1953 年、ニューヨーク生まれ。ユダヤ系米国人ビジネスマンで、作家にして活動家。コーネル大学卒業後、エルサレムのヘブライ大学に留学。帰国後にコーネル大学のロースクールで法学博士の学位を取得。知財関係のビジネスを起業、のちに売却。
水資源、国家安全保障、中東問題で「ニューヨーク・タイムズ」、「ウォールストリート・ジャーナル」等に寄稿、フォーリン・アフェアーズ外交問題評議会員、国際連合広報局のNGOセミナーなどで講演活動。ブロードウェイのミュージカルのリバイバル公演のプロデューサーをつとめるなど多彩な分野で活躍している。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものにWikipedia情報で加筆)
日本語訳者プロフィール秋山勝(あきやま・まさる)立教大学卒業。出版社勤務を経て翻訳の仕事に。訳書に『テクノロジーが雇用の75%を奪う』『アメリカの中学生はみな学んでいる「おカネと投資」の教科書』(以上、朝日新聞出版)、『アベベ・ビキラ』『死を悼む動物たち』『他人を支配したがる人たち』『若い読者のための第三のチンパンジー』(以上、草思社)。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたもの)
<関連記事>
・・危機的状態になる以前から、ハマスが実効支配するガザ地区の水問題が深刻だったことは、本書をよむとわかる
・・井戸水くみ上げ過ぎで、地下水位が下がり海面上昇しているガザ地区では、水源である地下水が飲料に適さなくなっている。そのうえ、さらに海水を流し込むことは、非人道的な行為としかいいようがない。水で世界から賞賛されたイスラエルのやることではないことに、イスラエルは気づくべきだ。イスラエルはさらに国際的レピュテーションを下げることばかりやっている。愚か者どもよ(怒)
(2023年12月16日 情報追加)
<ブログ内関連記事>
・・ドリップ灌漑など意すれる発の農業テクノロジーは、水テクノロジーあってこそ
書評『アップル、グーグル、マイクロソフトはなぜ、イスラエル企業を欲しがるのか?』(ダン・セノール & シャウル・シンゲル、宮本喜一訳、ダイヤモンド社、2012)-イノベーションが生み出される風土とは?
・・韓国人家族の米国入植を描いた『ミナリ』には水脈を発見するためのダウジングが登場
■日本の水
・・水さえ飲んでいれば人間はすぐに死ぬことはない。逆にいえば、水がなければ人間は死ぬ
(2023年11月25日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年12月23日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年6月24日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年11月19日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年10月22日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2020年12月18日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2012年7月3日発売の拙著です 画像をクリック!)
end















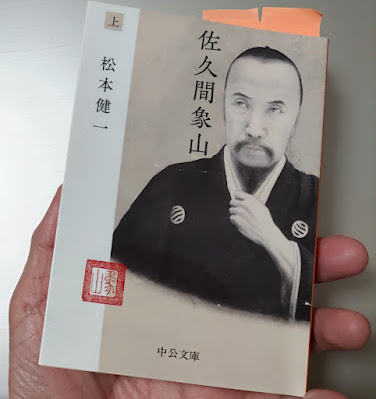




.png)





































