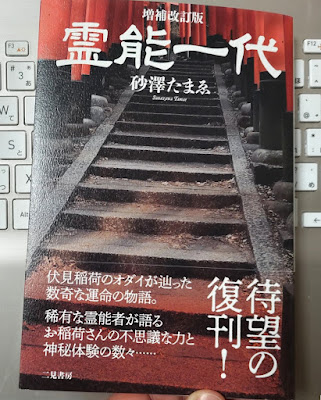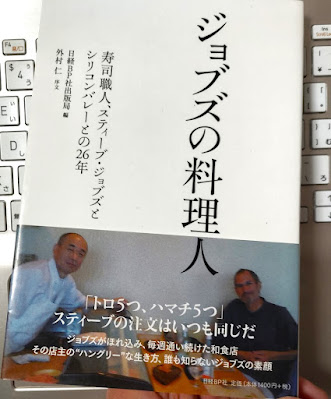「地下鉄サリン事件」から30年。1995年3月20日から30年。時間がたつのはあまりにも早い。30年といえば一世代である。
関西では阪神大震災、関東ではオウム事件。大規模自然災害に宗教テロ。「記憶」の風化は避けられないが、一方では30年もたてば、明らかになってきたことも少なくない。知られざる「記録」が発見され、記憶が消えないうちに記録となる。
1995年は、日本社会の底が抜けてしまった年として回顧されることになるだろう。
■オウム事件に対する「警視庁」の対応の真相
事件当時の「警察庁」の責任者に対する聞き取りである。いわばオーラルヒストリーとしての一次資料ということになる。
ここで「警察庁」とカッコ書きにしたのは、事件が発生した東京都は「警視庁」の管轄だが、全国の「都道府県警」を束ねるのが「警察庁」であることが、なにを意味しているのかを知る必要があるためだ。
現在では事件のかんする時系列が明らかになっているが、リアルタイムでは日本各地で起こった事件が、点と線で結ばれていなかったため、捜査に支障を来していたのである。面で行うべき広域捜査が難しかったのだ。
戦前は、組織上は内務省の下にあった警察は一元的に捜査をコントロールできたが、「戦後改革」のもとで内務省が解体され、地方自治の観点から都道府県単位に責任権限が委譲された。そのために発生したデメリットである。日本社会の問題点が露わになった事件でもあったのだ。
興味深いのは、当時は警察庁刑事局長だった垣見氏が、捜査計画を策定するにあたって、まずは先行事例を調査したという回想である。
戦前の宗教がらみの事件といえば、なんといっても1921年と1935年の二度にわたって実行された「大本事件」となる。
一般には「宗教弾圧」として理解されている大本教への強制捜査と教団施設の徹底破壊であるが、一般的な理解と捜査を担当した警察の立場はだいぶ違うことがわかる。
「大本事件」においても、特高による内偵にもとづいて捜査計画を策定し、強制捜査を実行しているのだ。この関連資料はぜひ見てみたいものだ。
ジャーナリストの江川紹子さん(・・高校の先輩でもある)は、YouTube番組のインタビューのなかで、それでも垣見氏はまだ語っていないことがあるのではないか、と言っていた。
「オウム事件」の全容が完全に明らかになるのは、まだまだ時間がかかりそうだ。
(画像をクリック!)
目 次巻頭言 手塚和彰第1章 松本サリン事件 1994年6月~10月第3章 対オウム作戦の立案 1994年9月末~121第3章 事件の続発と態勢構築 1995年1月~3月第4章 地下鉄サリン事件 1995年3月20・21日第5章 教団拠点の大捜索 1995年3月22日~3月中第6章 國松長官狙撃事件 1995年3月30日~5月第7章 麻原逮捕およびその後 1995年5月~1996年8月第8章 オウム事件全体の評価(1)― なぜ早期に捜索できなかったのか第9章 オウム事件全体の評価(2)― 30年後に振り返る付掲/事件の時系列表垣見隆とオウム捜査 ー ある警察官僚の出処進退(五十嵐浩司)垣見証言の意義(吉田伸八)終わらない事件と本書の位置 ー 後記にかえて(横手拓治)参考文献
著者プロフィール垣見隆(かきみ・たかし)1942(昭和17)年12月、静岡県浜松市生まれ。1965年、東京大学法学部卒業後、警察庁入庁。警視庁神田警察署長、福井県警察本部長、警察庁刑事局長、警察大学校長などを経て、1996(平成8)年、警察庁退職。1999年、弁護士登録。現在、第一東京弁護士会所属弁護士(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたもの)
■「サリン事件」に対する自衛隊の対応とその教訓
警察は事件捜査を行うが、警察だけでは対応できないのではないかという議論が警察内部でなされていたようだ。そのため自衛隊に頭を下げて協力を依頼したということを、垣見氏は語っている。
強制捜査にあたって、毒ガス対策として必要な防護服を自衛隊から借りたことがあげられる。これは「地下鉄サリン事件」が発生する前のことである。
そして、オウムと銃撃戦になった場合を想定して自衛隊の出動準備が行われていたことだ。いわゆる「治安出動」である。実際にはオウムは銃撃戦で応酬してくることはなかったが、その事実は知っておいたほうがよさそうだ。
実際に自衛隊が大車輪で活動したのは、「地下鉄サリン事件」における除染作業であった。世界ではじめて発生した「化学兵器テロ」である。 陸自の化学防護隊がクローズアップされているが、責任者として指揮をとったのは、陸上自衛隊第32普通科連隊長であった福山隆氏であった。化学防護隊との共同作業である。
その体験記で一次資料ともいうべき『「地下鉄サリン事件」自衛隊戦記 ー 出動隊指揮官の戦闘記録』(産経NF文庫、2025)を読んだ。初版は2009年の改訂版。ノンフィクション系の読み物として面白く読める本でもある。
都心では高層ビルによる電波障害があって無線がつかいにくいこと、30年前には携帯電話も普及していなかったため、軍隊にとって最重要の通信に苦労したことなど、当事者ならではのリアルの話も多い。
連隊長自身は除染現場には出動していないので、実際に出動し現場で活動した隊員たちの証言が複数収録されている。記録写真や映像からだけではわからない、当事者の心理状態までわかる。
圧巻とういうべきなのは「第8章 幻の作戦計画」であろう。「最悪の事態の備え」て秘密の作戦計画が策定されていたというのだ。
先にも見たように、「治安出動」が実行に移されることはなかったが、オウム真理教によるクーデターは未遂に終わったものの、けっして絵空事ではなかったのである。
問題は、米国はこの事件から多くの教訓を引き出しているのに対して、日本全体では教訓が十分に活かされているとは言い難いという指摘がなされていることにある。政府も防衛省も「公刊戦史」としてまとめていないのである。
ただし、東京都では石原元都知事のもとで教訓が活かされているというのが、数少ない救いというべきだろうか。2011年3月11日の「東日本大震災」の際にその教訓は活かされたことは記憶にあたらしい。
(画像をクリック!)
目 次《カラー写真集》自衛隊 "3・20" 出動記録まえがき第1章 第32普通科連隊第2章 大震災と防災訓練デモ第3章 事件発生第4章 留守部隊の奮闘第5章 出動準備第6章 出陣第7章 除染現場の闘い第8章 幻の作戦計画第9章 事件から得た戦訓資料1 「地下鉄サリン事件2」の概要資料2 神経剤とはなにかーサリンを中心に資料3 陸上自衛隊の化学科部隊資料4 除染隊出動記録ビデオよりあとがき【特別掲載】地下鉄サリン事件の現場で(芹沢伸生 当時産経新聞写真部記者)
著者プロフィール福山隆(ふくやま・たかし)1947年(昭和22年)、長崎県上五島・宇久島生まれ。佐世保北高から1970年(昭和45年)、防衛大学校(14期生)卒業。幹部学校指揮幕僚課程、外務省安全保障課出向、陸上幕僚監部防衛班・広報室、韓国防衛駐在官、第32普通科連隊長(地下鉄サリン事件時、除染隊派遣の指揮を執る)、陸幕調査第2課長(国外情報)、情報本部初代画像部長(衛星情報)、第11師団(札幌)副師団長、富士教導団長、九州補給処長などを歴任し2005年(平成17年)春、西部方面総監部幕僚長・陸将で退官。同年6月から2年間、ハーバード大アジアセンター上級客員研究員。現在、広洋産業株式会社顧問。(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたもの)
<ブログ内関連記事>
(2023年11月25日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年12月23日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2022年6月24日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年11月19日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2021年10月22日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2020年12月18日発売の拙著です 画像をクリック!)
(2012年7月3日発売の拙著です 画像をクリック!)
end